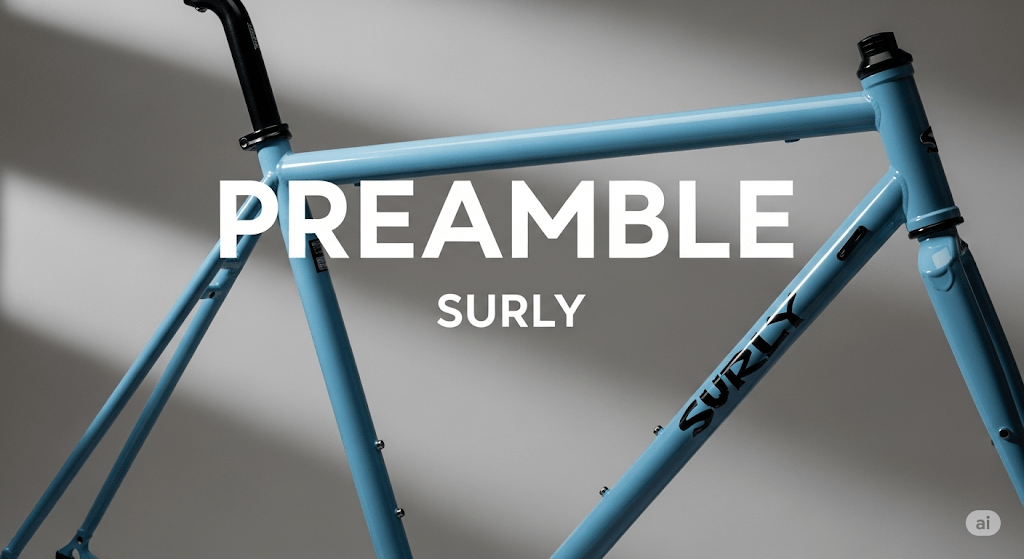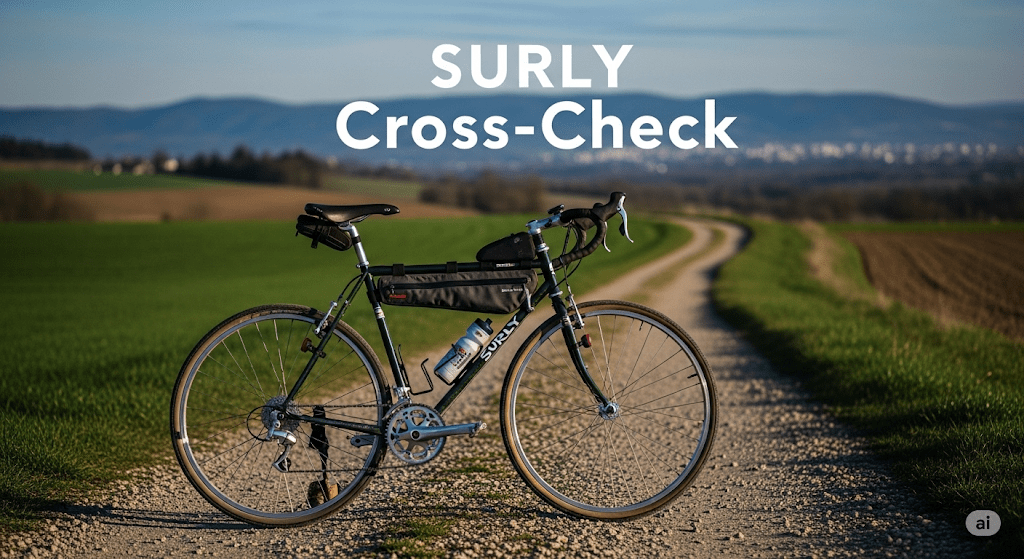Black Mountain Cycles “Mod.Zero” を徹底調査!- ゼロから生まれた、究極のオールロードフレームの物語

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕がずっと気になっていた一本のフレームについて、その魅力を余すところなくお伝えしたいと思います。カリフォルニア州ポイントレイズに拠点を置く小さなバイクカンパニー、「Black Mountain Cycles」が生み出したクロモリフレーム、”Mod.Zero”(モデル・ゼロ)。
何を隠そう、このフレームは、僕が今乗っているCrust BikesのEvasionを手に入れるとき、本当に、本当に最後の最後までどっちにしようか迷った一本なんです。Evasionが持つ、どこか無骨でワイルドな魅力に惹かれつつも、Mod.Zeroの持つ、より洗練された設計思想と、どんな乗り方にも応えてくれそうな懐の深さには、正直かなり心を揺さぶられました。だからこそ、このフレームには特別な思い入れがあって、いつか僕の言葉でその魅力を伝えたいとずっと思っていたんです。
このフレーム、ただのグラベルバイクやオールロードバイクという言葉で片付けることはできません。そこには、ビルダーであるマイク・バーレー氏の自転車に対する深い哲学と、時代の変化に対応しながらも本質を見失わない、誠実なモノづくりの姿勢が込められています。デザイナーという職業柄、僕はプロダクトの背景にあるストーリーや思想に強く惹かれるのですが、このMod.Zeroほど、その「背景」が魅力的なフレームはそう多くはありません。今回は、他のどの記事よりも深く、このフレームの本質に迫っていきたいと思います。
Mod.Zeroの誕生秘話:原点回帰から生まれた革新
Black Mountain Cyclesの創設者、マイク・バーレー氏。彼はHaroやMasiといった有名ブランドで長年プロダクト開発に携わってきた経験を持つ、まさに自転車業界のベテランです。彼が自身のブランドで生み出したフレームは、どれも華美な装飾を排し、長く使える実直な設計思想で多くのサイクリストから支持されてきました。

Mod.Zeroが生まれる直接のきっかけは、実は製造上の問題でした。それまで人気を博していた「MCD」と「Road+」という2つのモデルの生産継続が困難になったのです。多くのブランドならここで終わりかもしれませんが、マイク氏はこれを好機と捉えました。「2つのモデルの長所を融合させ、全く新しい一つのフレームをゼロから作ろう」と。
こうして始まったのが、”Model Zero”、すなわちMod.Zeroの開発です。MCDのジオメトリをベースに、より汎用性を高めるためのアップデートを施す。それは、これまでの歴史を受け継ぎつつ、未来を見据えた新たなスタンダードを創り出す作業でした。彼のブログには、この決断に至るまでの葛藤と、新しいフレームへの希望が綴られており、作り手の顔が見えるモノづくりとはこういうことかと、僕は深く感銘を受けました。
彼の作るバイクは、常に「乗り手」が中心です。流行りのスペックを追いかけるのではなく、「このバイクでどんな風に走ったら楽しいか」「どんな景色を見に行こうか」と、乗り手の想像力を掻き立ててくれる。Mod.Zeroは、そんなマイク氏の哲学が最も色濃く反映された、ブランドの新たな原点とも言える一本なのです。
ジオメトリを読み解く:Mod.Zeroが約束する最高のライド体験
自転車の乗り味を決定づける最も重要な要素、それがジオメトリです。ここでは公式サイトのジオメトリ表とサイズ情報を元に、Mod.Zeroの設計思想を紐解いていきましょう。
| サイズ | 44cm | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm |
| Seat Tube (c-t) | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
| Head Angle | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
| Seat Angle | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 72.5° | 72.5° |
| Top Tube (eff) | 530 | 540 | 555 | 575 | 595 | 615 |
| Chain Stay | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 |
| BB Drop | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 70 |
| Head Tube Length | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 |
| Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
| Trail | 64.1 | 60.8 | 60.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 |
| Stack | 567 | 588 | 607 | 627 | 646 | 665 |
| Reach | 368 | 366 | 370 | 383 | 391 | 405 |
| Standover | 756 | 778 | 802 | 828 | 851 | 875 |
【公式サイト準拠】サイズ別適応身長の目安
- 44cm: 152cm – 165cm (5’0″ – 5’5″)
- 47cm: 163cm – 173cm (5’4″ – 5’8″)
- 50cm: 170cm – 180cm (5’7″ – 5’11”)
- 53cm: 178cm – 185cm (5’10” – 6’1″)
- 56cm: 183cm – 191cm (6’0″ – 6’3″)
- 59cm: 188cm以上 (6’2″ +)
ジオメトリの注目ポイント
- 長めのヘッドチューブと高めのスタック値 Mod.Zeroのジオメトリでまず目に付くのが、長めに設計されたヘッドチューブです。これにより、スタック値(BB中心からヘッドチューブ上端までの垂直距離)が高くなり、スペーサーを多用しなくてもハンドルを比較的高めの位置に設定できます。これは、長時間のライドでも首や肩、腰への負担が少ない、リラックスした乗車姿勢を可能にします。レースバイクのような前傾姿勢ではなく、景色を楽しみながらマイペースで走るようなツーリングやグラベルライドに最適化された設計と言えるでしょう。
- 絶妙なBBドロップ BBドロップ(両輪のアクスルを結んだ線からBB中心までの下がり量)は、小さいサイズで72mm、大きいサイズで70mmに設定されています。これはグラベルバイクとしては標準的ですが、重心を適度に下げて安定性を確保しつつ、荒れた路面でのペダルヒットのリスクも軽減する絶妙なバランスです。700cホイールでも650Bホイールでも、バイクの性格を損なうことなく楽しめる懐の深さを示しています。
- サイズごとに最適化されたヘッドアングルとフォークオフセット 小さいサイズではヘッドアングルを寝かせ気味に、フォークオフセットを大きめに設定することで、小柄なライダーが乗った際のつま先と前輪の接触(トゥオーバーラップ)を防ぎ、ハンドリングの安定性を高めています。逆に大きいサイズではヘッドアングルを少し立て、オフセットを小さくすることで、キビキビとした反応性の良いハンドリングを実現。すべてのサイズで最高のライディング体験ができるよう、細やかに配慮されている点はさすがの一言です。
細部に宿るこだわり:Mod.Zeroのフレームスペック
デザイナーの視点から見ても、Mod.Zeroのスペックは非常に考え抜かれています。ここでは主要なスペックをピックアップし、その意味を解説します。
- ヘッドチューブ:44mmストレート 現代的な規格である44mmヘッドチューブを採用。これにより、付属の1-1/8″ストレートコラムフォークはもちろん、社外品のテーパーコラムのカーボンフォークなども装着可能になります。将来的なカスタムの幅が広く、剛性の確保にも貢献しています。
- タイヤクリアランス:700c x 50mm or 27.5″ (650b) x 2.25″ このフレームの最大の特徴とも言えるのが、この広大なタイヤクリアランスです。舗装路を軽快に走るなら700x35c、グラベルを攻めるなら700x45c、そして少しマウンテンバイク寄りのトレイルを楽しむなら27.5×2.25″といったように、走りたい道に合わせてタイヤとホイールを自由に選択できます。これ一台で、オンロードからオフロードまで、あらゆる冒険に対応できるでしょう。
- ブレーキ:フラットマウントディスク ロードバイクやグラベルバイクのディスクブレーキ規格として主流のフラットマウントを採用。制動力の高さはもちろん、見た目もスッキリと収まります。ローター径は最大160mmまで対応しており、どんな状況でも安心のストッピングパワーを発揮します。
- アクスル:12mmスルーアクスル (前100mm / 後142mm) ホイールの固定方法も現代的なスルーアクスル規格です。ホイール着脱時の位置決めが容易なだけでなく、足回りの剛性が格段に向上し、ディスクブレーキの制動力をしっかりと受け止めます。
- その他 シートポスト径は乗り心地の良さに定評のある27.2mm。フロントダブルにもシングルにも対応するケーブルルーティング、付属フォークにはボトルケージなどを取り付けられるアイレットも多数装備されており、バイクパッキングへの拡張性も申し分ありません。
こんな人におすすめしたい:Mod.Zeroという選択
では、このMod.Zeroはどんなライダーにフィットするのでしょうか。
- 一台の自転車で様々な道を走りたい人 週末のサイクリングロードから、林道や砂利道を探検するグラベルライド、荷物を積んでのバイクパッキングまで。このフレームなら、あなたの「走りたい」という気持ちにどこまでも応えてくれます。
- 長く付き合える、本質的な価値を持つ自転車が欲しい人 流行り廃りの激しい自転車業界の中で、Mod.Zeroの持つ価値は色褪せません。クロモリフレームのしなやかな乗り心地と堅牢性、そして考え抜かれた設計は、何年経ってもあなたにとって最高の相棒であり続けるでしょう。
- 自分で自転車を組む楽しみを味わいたい人 フレームセットから、自分のスタイルに合わせてパーツを一つ一つ選んでいく。Mod.Zeroはそんなビルドの過程も楽しめる、懐の深いフレームです。どんなパーツを組み合わせようか、想像するだけでワクワクしてきませんか?
ヒロヤス的おすすめビルド:Mod.Zeroのポテンシャルを最大限に引き出すパーツたち
もし僕がMod.Zeroを組むなら…と想像しながら、おすすめのビルドを考えてみました。コンセプトは「大阪の街乗りから週末の山遊びまで、気負わず楽しめる最高の日常冒険バイク」です。
- コンポーネント:SHIMANO GRX 600 (1×11速) グラベル専用設計のGRXは、操作性、耐久性ともにMod.Zeroにベストマッチ。フロントシングル仕様でトラブルを減らし、直感的な操作でどんな道でも楽しめます。
- ホイール:700c 手組み (ハブ: SHIMANO or DT SWISS / リム: VELOCITY AILERON) あえて手組みにこだわりたいですね。信頼性の高いハブに、汎用性の高いチューブレス対応リムを組み合わせます。普段使いからタフなライドまでこなせる、しなやかで壊れにくいホイールを目指します。
- タイヤ:Panaracer GravelKing SS 700x43c センタースリックパターンで舗装路は軽く、サイドのノブでコーナーや少し荒れた道でもグリップしてくれる、まさに万能タイヤ。日本の里山や林道にピッタリです。
- ハンドル:NITTO M137 Dirt Drop Bar 少しハの字に開いた形状が特徴のドロップハンドル。上ハンドルは握りやすく、下ハンドルは荒れた道でのコントロール性に優れています。見た目のクラシックな美しさもポイントです。
- サドル:BROOKS C17 Carved 天然ゴムベースで全天候に対応し、使い始めから快適な座り心地を提供してくれる名作サドル。中央の穴あき加工が、長距離での快適性をさらに高めてくれます。
まとめ
Black Mountain CyclesのMod.Zeroは、単なる高性能なフレームではありません。そこには、作り手であるマイク・バーレー氏の自転車への愛情と、乗り手への深い配慮が詰まっています。
製造上の都合という逆境を、「原点回帰」という創造的なエネルギーに変えて生み出されたこのフレームは、現代のサイクリストが求める多様なニーズに完璧に応えながらも、クロモリフレームならではの普遍的な魅力を失っていません。
考え抜かれたジオメトリは、長距離でも疲れにくい快適な乗り心地と、どんな道でも楽しめる安定したハンドリングを両立。700cと650Bのホイールを使い分けられるタイヤクリアランスは、この一台で無限の可能性が広がることを示唆しています。
もしあなたが、僕のようにCrustのEvasionのようなバイクとこのMod.Zeroで迷っているなら、あるいはスペック表の数字だけでは測れない、自転車との対話を楽しめるような一台を探しているのなら、Mod.Zeroは最高の選択肢になるはずです。このフレームと共に、まだ見ぬ景色を探しに出かけてみませんか?
この記事を読んで、Mod.Zeroに興味を持った方、あるいは既に乗っているよ!という方がいらっしゃれば、ぜひコメントであなたのビルドやライドの経験を教えてください。皆さんの声が、他の誰かの素晴らしい自転車ライフのきっかけになるかもしれません。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!