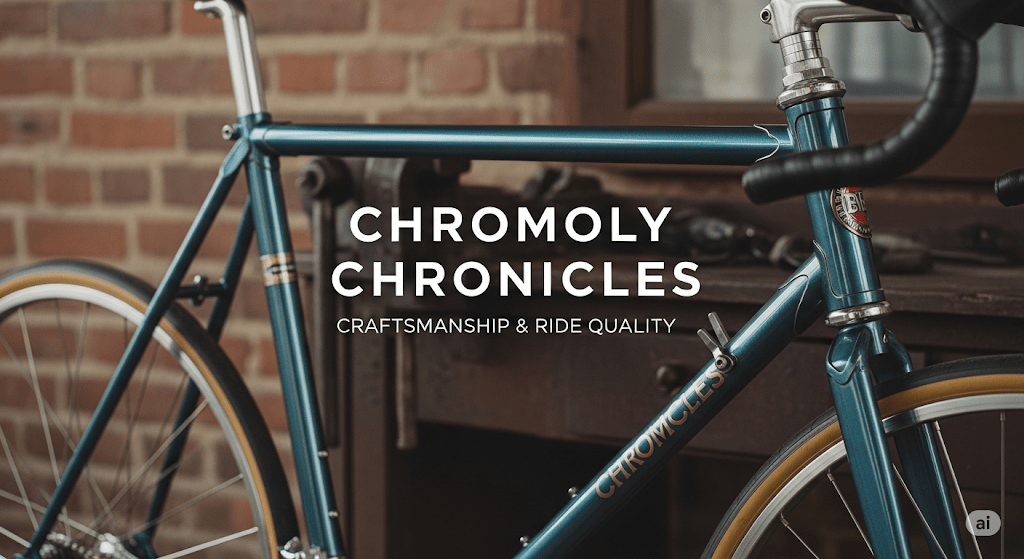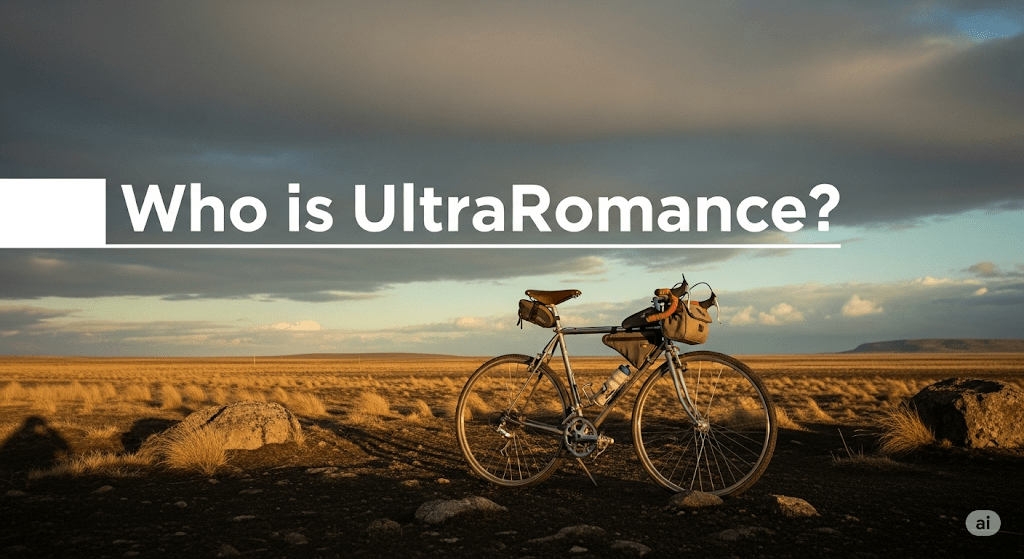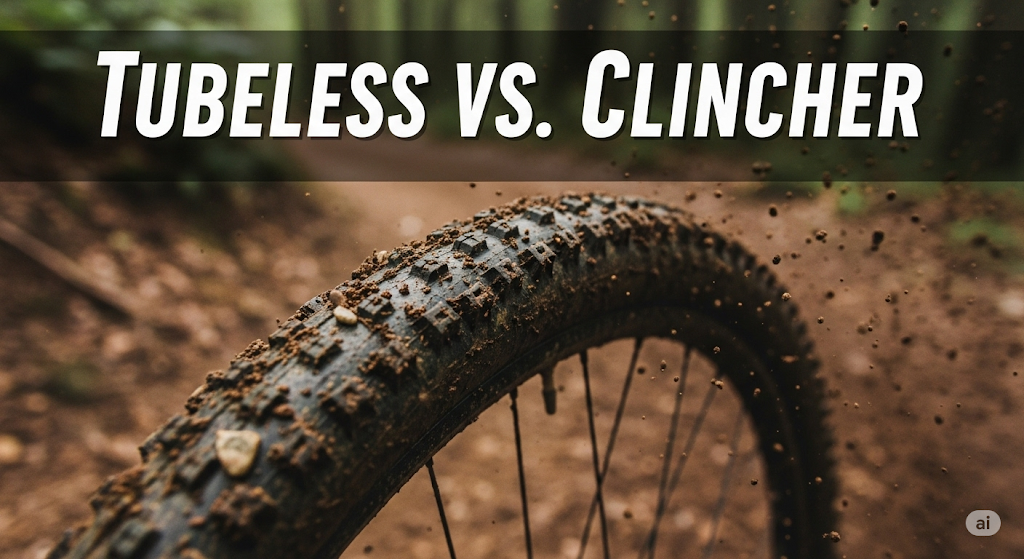雨の日も「美学」を諦めない。クロモリ乗りが考える「簡易フェンダー」という選択肢

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は「簡易フェンダー(泥除け)」について、僕なりの考えをお伝えしたいと思います。
ここ数日の大阪は、スッキリしない天気が続いていました。雨が降ったかと思えば、急に晴れ間が覗いたり。こういう時期に自転車乗りとして悩ましいのが、「泥はね」ですよね。
特に僕らが好むクロモリのバイクは、その細身のシルエット、フレームの美しさが命です。そこに「いかにも」という感じのフルフェンダー(本格的な泥除け)を装着することに、デザイナーとして、そして一人の自転車好きとして、どうしても抵抗を感じてしまう瞬間があります。
もちろん、フルフェンダーが持つ完璧な防御性能は素晴らしいものです。雨の日も背中や足元を汚さず快適に走れるあの感覚は、一度味わうと手放せなくなる魅力があります。
ですが、晴れた日にそのフェンダーが「装備」として車体についている状態を想像すると……うーん、ちょっと違うんだよな、と。僕のグラベルロードやMTBには、もっとこう、軽快さが欲しい。
そんなジレンマを抱える僕たちにとって、非常にスマートな解決策となるのが「簡易フェンダー」という存在です。
今回は、この「簡易フェンダー」が持つ魅力と、デザイナーという視点から見たその「美学」について、少し掘り下げてみたいと思います。
なぜフルフェンダーではなく、「簡易」なのか
自転車におけるフェンダー(泥除け)は、大きく分けて2種類あります。
ひとつは、先ほども触れた「フルフェンダー」。タイヤをほぼ半周覆うような形状で、専用のダボ穴(ネジ穴)やステー(支柱)を使ってフレームにガッチリと固定するタイプです。その防御力は絶大で、路面がウェットな状態でも、水や泥が背中や顔に飛んでくるのをほぼ完璧に防いでくれます。ランドナーやコミューター(通勤用自転車)など、天候を問わず走ることを前提とした自転車には最適な装備です。
しかし、その反面、一度取り付けると外すのが億劫であること、重量がそれなりに増えること、そして何より、バイク全体のシルエットが大きく変わってしまうことが挙げられます。
特に、ダボ穴が設けられていないピュアなロードバイクや、太いタイヤを履かせるためにクリアランス(隙間)がギリギリなMTB、そして美観を重視する僕たちのクロモリバイクにとって、フルフェンダーは「オーバースペック」あるいは「装着不可」となるケースも少なくありません。
そこで登場するのが「簡易フェンダー」です。
サドルレールやシートポスト、あるいはダウンチューブにストラップやバンドで「一時的に」取り付けることを前提としたフェンダー。
もちろん、防御性能はフルフェンダーに劣ります。「完璧に防ぐ」というよりは、「最悪の事態(背中に一本、泥の線がビシャッと入るなど)を防ぐ」というレベルのものがほとんどです。
ですが、その最大のメリットは「手軽さ」と「デザインへの介入度の低さ」にあります。
デザインと機能性の「最適解」を探る
僕が簡易フェンダーに惹かれるのは、それが「機能主義的なデザイン」の宝庫だからです。
「最小限の面積で、最大の効果を」。
この命題に対して、各ブランドがそれぞれのアプローチで回答を出しているのが面白い。デザイナーとしての視点で見ると、そこには「割り切り」の美学があります。
例えば、サドルレールに差し込むだけの小さな樹脂製の板。あれは「お尻」だけを守ることに特化しています。脚やフレームは濡れるかもしれない。でも、ライド後にカフェに入った時、背中が汚れていて恥ずかしい思いはしなくて済む。それで十分じゃないか、というわけです。
また、バイクパッキングやグラベルライドの文脈で簡易フェンダーの存在感は増しています。オフロード走行後の泥だらけのバイク。それはそれでカッコいいのですが、問題はウェアや機材へのダメージです。簡易フェンダー一枚あるだけで、サドルバッグへの泥の付着が劇的に減ったり、フロントフォークのシール部分(サスペンションの可動部)へのダメージを軽減できたりします。
「必要ない時は外しておく」というスマートさ。 「必要な時だけ、その機能を利用する」という合理性。
これは、僕たちがクロモリバイクという「普遍的な道具」に、現代的なパーツを組み合わせて自分なりのスタイルを追求する感覚と、とても近いものがあると思うのです。
シーンを代表するプロダクトたち
では、具体的にどのような製品があるのか。僕が注目している、いくつかの代表的なプロダクトを紹介したいと思います。
Ass Savers(アスセイバーズ)
簡易フェンダーのムーブメントを語る上で、このブランドは外せません。スウェーデン・ヨーテボリで生まれた彼らの製品は、まさに「ミニマリズムの極致」です。
代表的な「Ass Saver Regular」は、その名の通り「お尻を守る」ためだけのもの。使わない時は折り畳んでサドルの下に隠しておけるというアイデアは、革新的でした。
最近では「WIN WING 2」という、タイヤのすぐ上(シートステー)に固定するタイプも登場しています。これは従来のサドルレールタイプよりも格段に防御力が高く、特にグラベルシーンで注目を集めています。デザインも非常に洗練されており、バイクの美観を損ねないギリギリのラインを攻めている感じがします。
SKS(エスケーエス)
1921年創業、ドイツの老舗自転車パーツブランドであるSKS。ドイツ製品らしい「質実剛健」さと「機能美」を併せ持つ製品群が魅力です。
簡易フェンダーの分野でも、「S-BOARD」(フロント用)や「S-BLADE」(リア用)が定番です。これらは工具不要のラバーストラップで固定でき、着脱が非常に簡単。 リア用の「S-BLADE」はシートポストに固定するタイプですが、角度調整が細かくできるため、泥はねの軌道を計算して最適化できます。
派手さはありませんが、「道具」としての信頼感は抜群。長く使い続けられる安心感があります。
TOPEAK(トピーク)
独創的なアイデアと高い実用性で、世界中のサイクリストから支持される台湾のブランド、TOPEAK。
彼らの「DeFender(ディフェンダー)」シリーズは、非常にラインナップが豊富です。MTB向けの大型のものから、ロードバイク用のスリムなものまで。
特にユニークなのは、フェンダーの後端にLEDライトを内蔵した「DeFender iGlow」のようなモデル。安全性と機能を両立させるという、いかにもTOPEAKらしい合理的な発想です。 着脱機構もクイックリリース式で扱いやすく、「かゆいところに手が届く」製品づくりはさすがの一言です。
まとめ
簡易フェンダーは、決して「フルフェンダーを買えない人の妥協の産物」ではありません。
それは、「自転車に乗るスタイル」や「美意識」に基づいて、機能を選択する「賢い選択」なのだと僕は思います。
もちろん、土砂降りの雨の中を毎日通勤するのであれば、フルフェンダーが最適解です。 しかし、僕のように「基本は晴れた日に走る。でも、雨上がりや、ちょっとしたオフロードも楽しみたい。そして何より、愛車のスタイルは崩したくない」と考える人間にとって、簡易フェンダーは最高の相棒になってくれます。
たった一枚の樹脂の板が、雨上がりのライドの憂鬱さを取り払い、自転車に乗る楽しみを継続させてくれる。
皆さんも、ご自身のライドスタイルやバイクのデザインに合わせて、「最小限の防御」という美学を取り入れてみてはいかがでしょうか。
あなたの愛車に似合う「一枚」が、きっと見つかるはずです。
皆さんは簡易フェンダー、使っていますか? もし「こんな使い方してるよ」「このブランドがおすすめ」というのがあれば、ぜひコメントで教えてください。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!