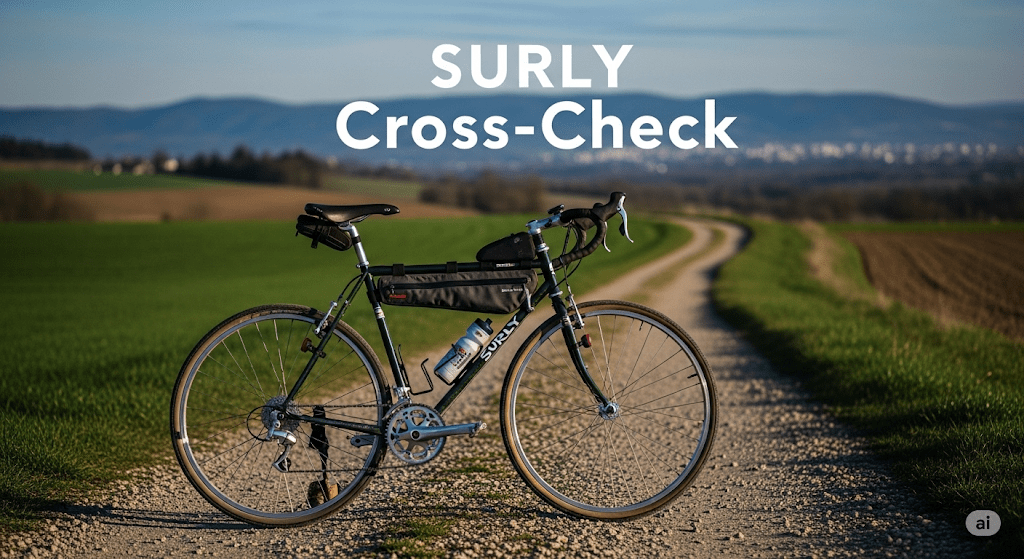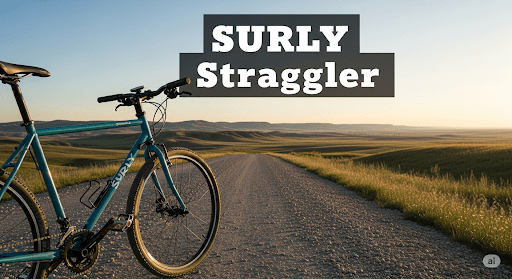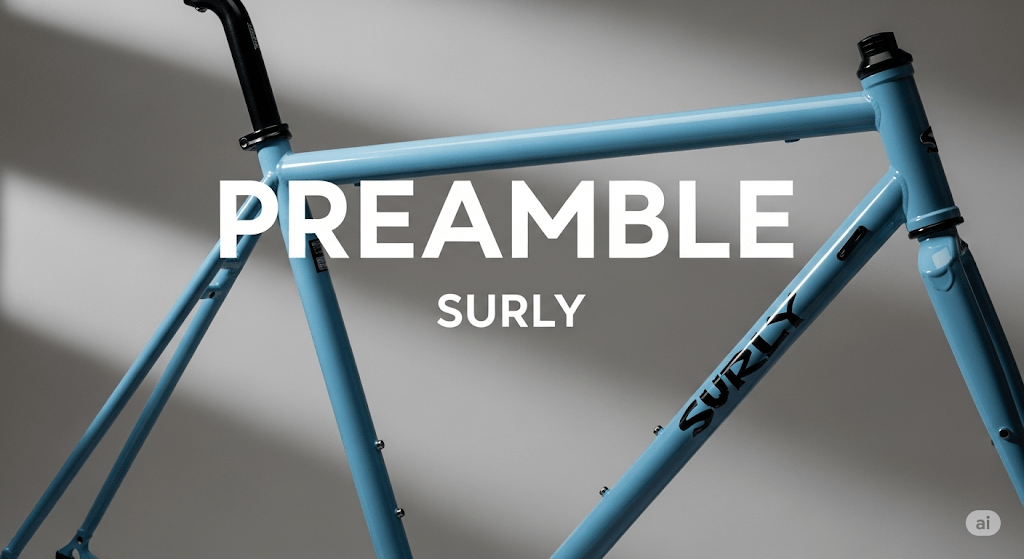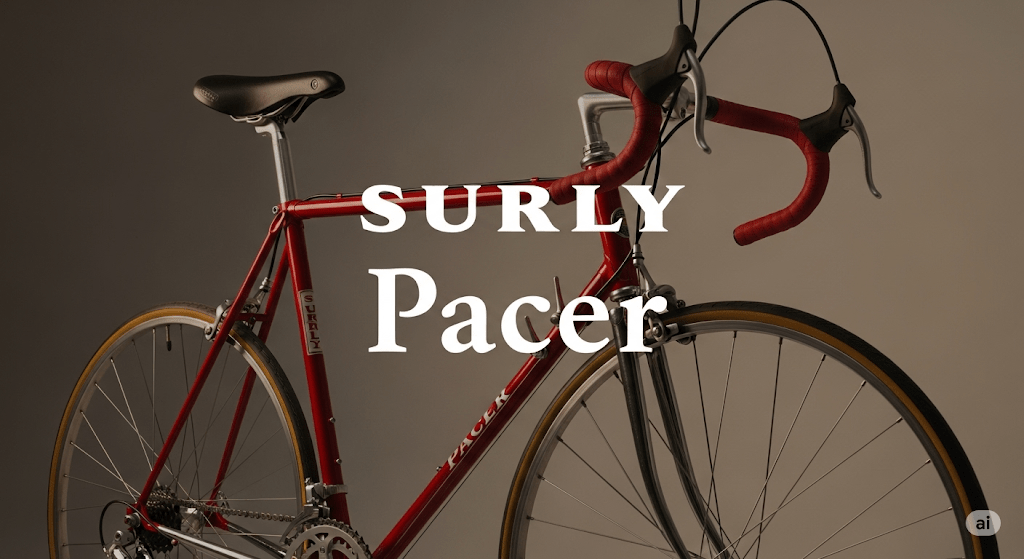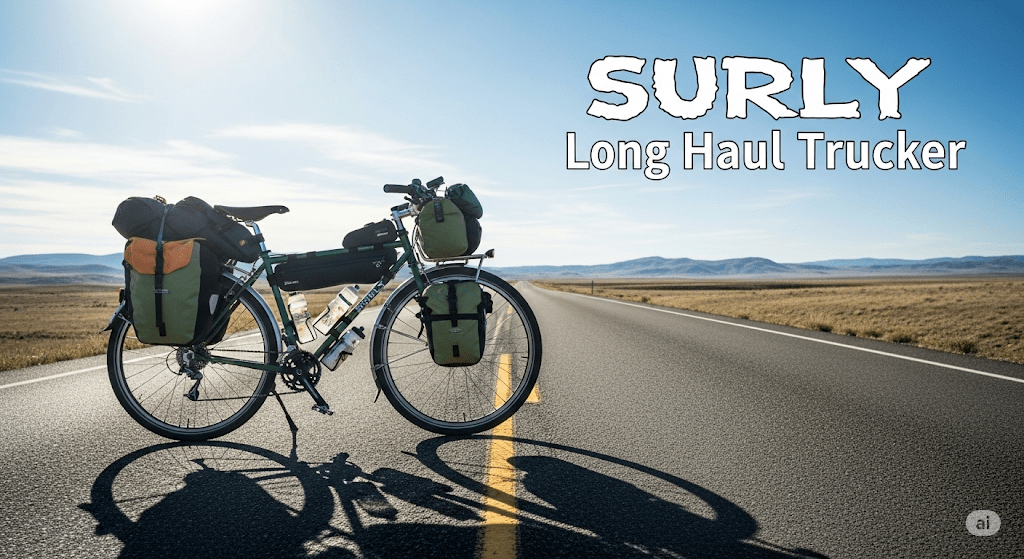Surly Bridge Club:街も、裏道も、思いのままに駆け抜ける、最強の遊び道具

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。今回は、Surlyのラインナップの中でも、特に遊び心と実用性を兼ね備えた、僕のお気に入りのフレーム、**Bridge Club(ブリッジ・クラブ)**について、深く掘り下げていきたいと思います。
このフレームは、特定の用途に特化するのではなく、**「自転車に乗るのが楽しい」**という根源的な喜びを思い出させてくれます。なぜこのフレームが、通勤から週末の冒険まで、僕たちの日常と非日常の境界をシームレスに繋いでくれるのか。その秘密を、メーカーの思いやフレームの細部にまで触れながら、僕なりに解説していきます。
Bridge Clubに宿るメーカーの思い
Bridge Clubは、Surlyの哲学である**「タフで、シンプルで、実用的」**という思想を、より多くのライダーに向けて、親しみやすい形で具現化したものです。
ヒストリーとコンセプト
LHTやOgreといったSurlyの定番ツーリングバイクが、アメリカの広大な荒野でのツーリングや、世界を股にかける壮大な旅をコンセプトにしているのに対し、Bridge Clubはもっと身近な冒険に焦点を当てています。
国土の殆どが舗装されている日本においては、ほぼ最大規模の日本1週を含め、最も適した選択肢のうちの一つと言えるでしょう。
このフレームにメーカーが込めたコンセプトは、**「仲間とライドに出かけ、橋の下でサンドイッチをかじっている、そんな自転車に乗っていない時間にあえてフォーカスした」**というものです。
これは、ただ速く走ることや遠くへ行くことだけが自転車の楽しみではない、というSurlyからのメッセージです。ライドの途中で立ち止まって景色を眺めたり、仲間と他愛もない話で盛り上がったり、美味しいものを食べたり。Bridge Clubは、そんな**「ライドの過程で生まれる時間や体験」**を大切にしてほしい、という思いを形にしたフレームなんです。
華美なデザインや複雑な機構は一切なく、ただひたすらに「シンプルで、何でもできる」ことを追求した、まさに**「究極の万能フレーム」**なんです。
Bridge Clubが持つ魅力
- 圧倒的な汎用性:一つのフレームで、通勤用のコミューター、ライトツーリングバイク、そしてグラベルバイクとしても使える高い汎用性を備えています。
- 抜群のタイヤクリアランス:27.5インチと700cの両方のホイールサイズに対応し、さらに極太のタイヤを履かせることができます。これにより、ライドする場所に合わせて、乗り味をガラリと変えられます。
- 驚くほどの互換性:MTB、ロード、グラベルなど、様々なパーツ規格に対応しているため、手持ちのパーツを流用しやすく、気軽にカスタムを楽しめます。
Bridge Clubの乗り味を形作るジオメトリとスペック
次に、Bridge Clubの「乗り心地」や「使い勝手」を決定づけている、具体的なジオメトリとスペックを見ていきましょう。
Bridge Clubのジオメトリ表
| サイズ | Seat Tube Length | Top Tube Length(Effective) | Head Tube Angle | Seat Tube Angle | BB Drop | Chainstay Length |
| XS | 335.6mm | 545mm | 70° | 73° | 60mm | 435mm |
| S | 406.4mm | 570mm | 71° | 73° | 60mm | 435mm |
| M | 457.2mm | 595mm | 71° | 73° | 60mm | 435mm |
| L | 508mm | 615mm | 71° | 73° | 60mm | 435mm |
| XL | 558.8mm | 630mm | 71° | 73° | 60mm | 435mm |
ジオメトリから読み解くBridge Clubのキャラクター
- チェーンステーの長さ(435mm): Long Haul Truckerの460mmと比べると短く、Midnight Specialの425mmと比べるとわずかに長いです。この絶妙な長さが、直進安定性と軽快さのバランスを生み出しています。荷物を積んだ時の安定感を確保しつつ、空荷での街乗りや、ちょっとしたトレイルでも扱いやすい、まさに「万能」なジオメトリです。
- BBドロップ(60mm): BBドロップは比較的浅く設計されています。これにより、ペダルが地面に接触するリスクを減らし、悪路での走行をより安全なものにしています。
- ヘッドチューブアングル(70°〜71°): サイズごとに角度が調整されていますが、全体的に寝かせ気味のヘッドアングルは、ハンドリングを意図的に鈍くしています。これは荷物を積んだ状態で、不意なハンドル操作でバランスを崩すことを防ぐためです。ゆったりと、どっしり構えて走るための設計なんです。
フレームのスペックに言及する
- フレーム素材:Surly CroMoly Surlyのアイデンティティとも言えるクロモリ素材。タフで耐久性が高いのはもちろん、しなやかで路面からの振動を吸収してくれるため、長時間のライドでも疲れにくい乗り心地を提供します。
- エンド幅:フロント100mm、リア135mm このフレームの最大のセールスポイントの一つです。クイックリリースとスルーアクスルの両方に対応するGnot-Boost規格を採用しています。これにより、手元にある様々なホイールを装着することが可能となり、ビルドの幅が大きく広がります。
- BB規格:68mm幅のJIS(BSA)ねじ切り この規格は汎用性が高く、メンテナンスが非常に容易です。異音トラブルも少なく、旅の途中で自分でBB交換を試すこともできるので、DIY派のライダーには嬉しいポイントです。
- タイヤクリアランス:27.5インチ x 2.8インチ / 700c x 47mm このフレームの持つ「万能性」を象徴するスペックです。ロードタイヤから、セミファットなMTBタイヤまで、あらゆるタイヤを履かせることができます。
ヒロヤス的おすすめビルド:Bridge Clubを最高の遊び道具にする
もし僕が今、Bridge Clubをゼロからビルドするなら、このフレームの持つ「汎用性」を最大限に引き出すコンセプトでパーツを選びます。
「街乗りからちょっとしたバイクパッキングまで、気軽な冒険を楽しむビルド」
コンポーネント
- シマノ Deore 1x シンプルで信頼性が高く、幅広いギアレンジが魅力です。フロントシングルにすることで、変速操作をシンプルにし、チェーン落ちのリスクも減らせます。
ヘッドパーツ
- Chris King NoThreadSet™ シンプルで無骨なSurlyのフレームに、あえてChris Kingのヘッドパーツを組み合わせることで、さりげないアクセントを加えます。美しいアルマイトカラーは、バイクの表情をガラリと変えてくれます。その圧倒的な耐久性と滑らかな回転性能は、まさに一生モノ。長く大切に乗りたいバイクにこそ、選んでほしい逸品です。
ホイール
- リム:WTB i23 丈夫でチューブレスにも対応するWTBのリム。様々なタイヤサイズに幅広く対応できます。
- ハブ:Shimano Deore Hub あえて最高級のハブではなく、Deoreのハブを選びます。耐久性が高く、世界中のどこでもスペアパーツが手に入りやすいからです。
クランク
- Formosa シングルクランク 台湾の老舗ブランドが手掛けるFormosaのクランクは、削り出しの美しいルックスと高い剛性を両立しています。シンプルで無骨なBridge Clubのフレームに、モダンでシャープな雰囲気をプラスしてくれます。
その他
- ハンドル:Sim Works by NITTO “The Towel Rack Bar” ご提案いただいたタオルラックバーは、このフレームのコンセプトにぴったりです。大きく広がるフレア形状が特徴で、ドロップ部分を握った際の安定感が抜群。悪路でのコントロール性を高め、リラックスしたライドポジションを可能にします。
- タイヤ:Schwalbe G-One Allround(27.5×2.25) 舗装路でも軽快に走れて、グラベルでも十分なグリップ力を発揮します。
- キャリア:Surly 8-Pack Rack フレームのフロントに小型のキャリアを装着。日々の買い物や、週末のキャンプツーリングにも使える、実用的なセットアップです。
まとめ:Bridge Clubは、自転車に乗る喜びを思い出させてくれる
Bridge Clubは、究極のロードバイクでもなければ、最先端のグラベルバイクでもありません。
このフレームは、ただひたすらに、「自転車に乗ってどこかへ行く」というシンプルな行為の楽しさを思い出させてくれる存在です。近所の公園へ、河川敷へ、そしていつか、ずっと行ってみたかったあの場所へ。
Bridge Clubは、ライダーが求めるどんな冒険にも応えてくれる、最高の遊び道具です。
速さや軽さを追い求めるだけではない、自転車本来の喜びを求めている人。そんなあなたの最高の相棒として、Bridge Clubほど頼もしいフレームは、そう多くはないでしょう。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!
Surlyの自転車は、独自のスタイルと哲学を持つショップで取り扱われていることが多いです。ここでは、日本全国の代表的なSurly取扱店をいくつかご紹介します。
- 店舗名: Blue Lug (ブルーラグ)
- 地域: 東京都
- 自転車を愛する人々が集まる、東京を代表するカスタムバイクショップ。Surlyをはじめとする個性的なブランドを多数扱い、独自のセンスで組み上げられた自転車は多くのファンを魅了しています。パーツの品揃えも豊富で、気軽に相談できる雰囲気も魅力です。
- 公式ホームページ: https://bluelug.com/
- 店舗名: Circles (サークルズ)
- 地域: 愛知県
- 名古屋を拠点に、自転車文化の発信地として知られるショップ。Surlyの魅力を深く理解し、ライフスタイルに合わせた提案をしてくれます。併設されたカフェ「Earlybirds Breakfast」も人気で、自転車好きのコミュニティスペースとしても機能しています。
- 公式ホームページ: https://www.circles-jp.com/
- 店舗名: Movement (ムーブメント)
- 地域: 大阪府
- 大阪市内に店舗を構える、カスタムバイクのプロショップ。Surlyの魅力を深く理解しており、ユーザーのスタイルや用途に合わせたオリジナルの1台を丁寧に組み上げてくれます。街乗りから本格的なツーリングまで、Surlyの多様な楽しみ方を提案してくれるでしょう。
- 公式ホームページ: https://movement-cycle.com/
- 店舗名: grumpy (グランピー)
- 地域: 広島県
- 広島県で長年Surlyを取り扱っている老舗ショップ。独自のイベントやライド企画も盛んで、Surlyを通じて広がる自転車の楽しみ方を提案しています。バイクパッキングやグラベルライドなど、Surlyの魅力を最大限に引き出すカスタムを得意としています。
- 公式ホームページ: https://ride.grumpy.jp/
- 店舗名: サイクルハウス ウエスタン
- 地域: 愛媛県
- 愛媛県にあるスポーツバイクショップ。Surlyの魅力を深く理解しており、グラベルロードやツーリングバイクなど、幅広いモデルの提案を得意としています。カスタムの相談にも親身に乗ってくれるので、安心して任せられます。
- 公式ホームページ: https://www.ch-western.com/
- 店舗名: 正屋 (MASAYA)
- 地域: 福岡県
- 福岡市にあるスポーツバイク専門店で、Surlyの取り扱いも豊富。ロードバイクやマウンテンバイクはもちろん、ツーリングや通勤に使えるSurlyの楽しみ方を提案してくれます。親しみやすい雰囲気も特徴です。
- 公式ホームページ: https://www.masaya.com/
- 店舗名: chillnowa (チルノワ)
- 地域: 北海道
- 函館市を拠点とする自転車ショップ。雪国ならではのファットバイク文化を牽引しつつ、様々なSurlyのバイクを扱っています。個性的なカスタムを得意とし、Surlyを遊び倒すスタイルを提案してくれるでしょう。
- 公式ホームページ: http://www.chillnowa.com/
- 店舗名: TairaCycle (タイラサイクル)
- 地域: 沖縄県
- 沖縄県北谷町にある自転車ショップ。Surlyの正規取扱店として、レースから街乗りまで幅広いニーズに対応しています。沖縄の美しい景色をSurlyで楽しむための提案をしてくれるでしょう。
- 公式ホームページ: https://www.tairacycle.com/
記事を読んでSurlyの自転車が気になったら、是非近くのお店に足を運んで実物を見たり、試乗車があれば体験させてもらうのもいいですね!
※上記は代表的な店舗の一部です。最新の取扱状況や在庫については、各店舗のホームページやSNSをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
こんな記事も読まれています

 17:26
17:26