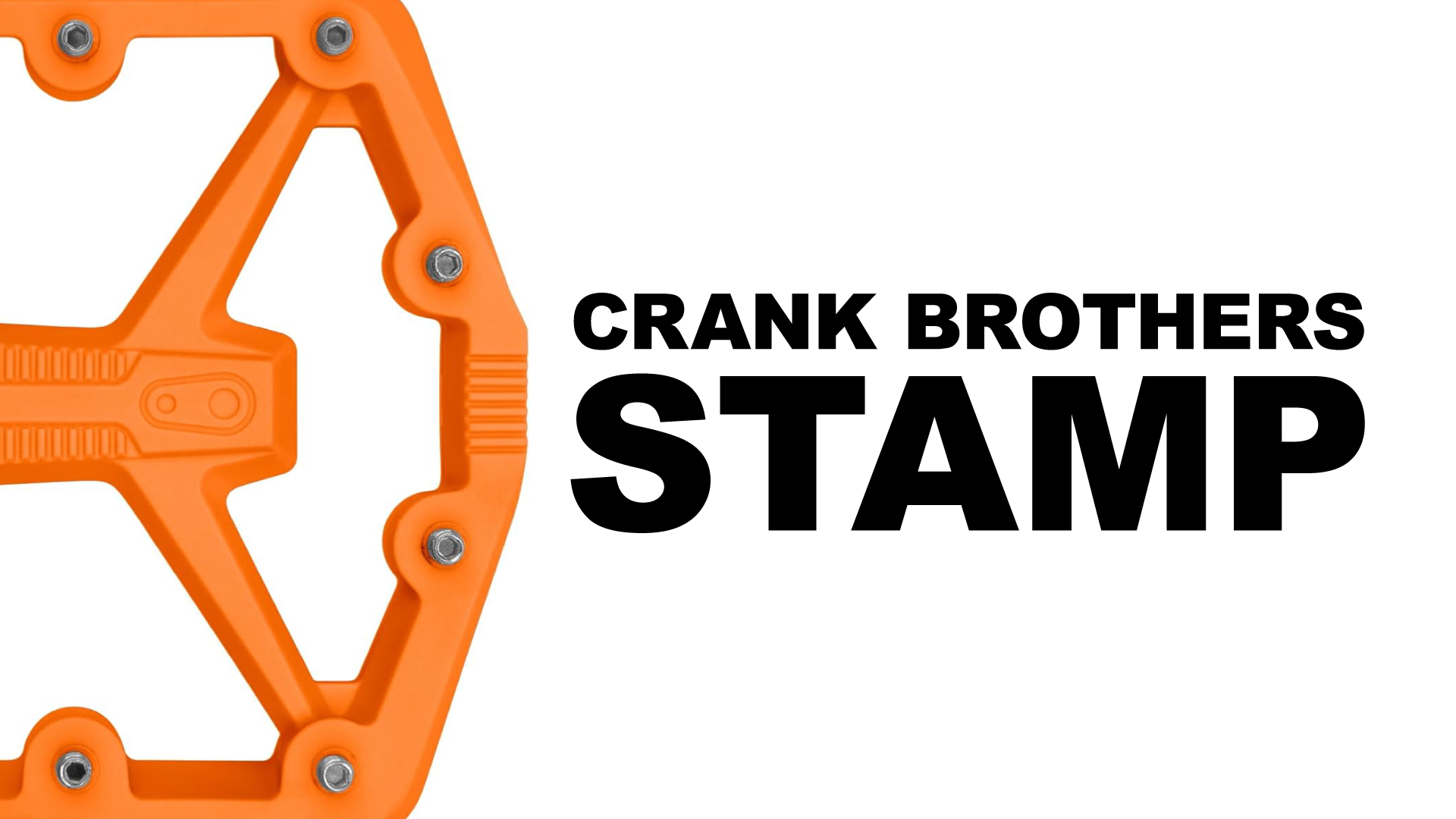「hi-bar」「hihi-bar」NITTOとBLUE LUGが生んだ名作ハンドルバーの知られざる正体に迫る!

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。
さて、今回は僕たちが何気なく握っている自転車の「ハンドル」に焦点を当て、その中でも特に深い物語を持つプロダクトについてお伝えしたいと思います。それは、日本の老舗パーツメーカーNITTO(日東)と、東京を拠点に世界中の自転車好きを魅了するバイクショップBLUE LUG(ブルーラグ)**のコラボレーションによって生まれた「hi-bar(ハイバー)」と「hihi-bar(ハイハイバー)」です。
僕自身、デザイナーという仕事柄、モノの背景にあるストーリーや作り手の哲学に強く惹かれます。なぜこの形なのか、どんな想いで作られたのか。
それを知ることで、プロダクトへの愛着は格段に深まりますよね。この2本のハンドルバーは、まさにそんな物語に満ち溢れた名作。今回は、その誕生秘話から素材選定のドラマ、デザインの細部、そして作り手の想いまで、じっくりと掘り下げていきたいと思います。


すべては一本のビンテージハンドルから始まった
この物語の始まりは、BLUE LUGの敏腕メカニックであり、数々の名作オリジナルパーツのデザイナーでもある金子さんが、一本の古いBMXハンドルに出会ったことに遡ります。
それは80年代のビンテージBMXに付いていたハンドルで、高すぎず、低すぎず、そして絶妙な手前への曲がり(バックスイープ)を持つ、なんとも言えない魅力的な形状をしていました。
当時のマウンテンバイク(MTB)やBMXのハンドルは、今の基準で見るとライズ(高さ)が控えめなものが主流。
しかしそのハンドルが持つ独特の「高さ」と「引き」は、リラックスした乗車姿勢を生み出し、視界を広げ、街中をゆったりと流すのに、これ以上ないほど心地よいものでした。
「この乗り心地を、現代の規格で、もっと多くの人に届けたい」。
その想いが、新しいハンドルバー開発の原点となったのです。それは単なる復刻ではなく、ビンテージへの敬意を払いながらも、現代の多様な自転車にフィットする新しい価値を生み出す挑戦の始まりでした。
老舗メーカーNITTOとBLUE LUGの幸福な出会い
このアイデアを実現させるパートナーとして白羽の矢が立ったのが、日本の自転車パーツ業界の至宝、NITTOでした。
1923年創業という100年以上の歴史を持つNITTOは、その卓越した金属加工技術で世界中にその名を知られています。競輪選手が使うNJS認定のステムやハンドルから、旅好きのためのキャリアまで、彼らの作る製品は常に「信頼」の二文字と共にあります。機能一辺倒ではなく、工芸品のような佇まいを併せ持つのがNITTO製品の真骨頂。僕のようなモノ好きにはたまらないブランドです。
一方のBLUE LUGは、単なる自転車屋ではありません。
自分たちの「好き」を突き詰め、それをオリジナル製品として形にし、独自の自転車カルチャーを発信し続けるクリエイティブ集団です。彼らのフィルターを通して生まれる製品は、常に実用的でありながら遊び心に溢れ、世界中のサイクリストから熱烈な支持を受けています。
そんな両者がタッグを組む。ビンテージへの深い造詣と柔軟な発想を持つBLUE LUGのアイデアを、NITTOが世界最高峰の技術で形にする。
このコラボレーションは、名作が生まれるべくして生まれた、幸福な出会いだったと言えるでしょう。
ハンドルに込められた思想。デザイナー金子さんという人物
この「hi-bar」「hihi-bar」を語る上で絶対に欠かせないのが、生みの親であるBLUE LUGの金子さん(愛称:金やん)の存在です。
彼はBLUE LUG幡ヶ谷店のチーフメカニックでありながら、同社のオリジナルパーツのデザインを数多く手掛けるキーマン。彼のInstagramを見れば、ビンテージMTBから最新のグラベルバイクまで、古今東西のあらゆる自転車への深い愛情と知識を持っていることが伝わってきます。
金子さんのデザインの根底にあるのは、常に「乗り手」としての視点です。「どうすればもっと快適になるか」「どうすればもっと格好良くなるか」という問いを、豊富な経験と知識、そして卓越したセンスで解き明かし、形にしていく。
彼が生み出す製品は、決して奇をてらったものではありません。自転車の歴史の中に確かなルーツを持ちながら、現代の僕たちの乗り方に寄り添う、絶妙な「さじ加減」が魅力なのです。
このハンドルに込められたのも、まさにその哲学。「楽な姿勢で、広い視野で、街の景色を楽しんでほしい」。そんなシンプルな想いが、あの美しい曲線の中に凝縮されています。
素材を巡るドラマ。「hi-bar」と「hihi-bar」徹底解説
さて、いよいよプロダクトそのものを見ていきましょう。この2つのハンドルは、見た目は似ていますが、実は素材と開発経緯に面白いストーリーが隠されています。
当初、金子さんが思い描いていたのは、ビンテージハンドルのようなルックスを持つクロモリ製のハイライズバーでした。しかし、試作品をNITTOの厳しい強度試験にかけたところ、残念ながらクリアすることができませんでした。NITTOからの提案は「クロスバー(補強のブリッジ)を入れれば強度は確保できる」というもの。
この提案が、結果的に2つの異なる名作を生み出すきっかけとなります。
B903 “Hi-Bar” (アルミニウム)
まず、クロスバーなしのシンプルなスタイルを実現するために、素材をクロモリからアルミニウムに変更して開発されたのが「hi-bar」です。 強度を確保するために、NITTOの得意とする焼き入れ(HEAT TREATED)処理が施されたアルミパイプを使用。
これにより、高いライズと広いハンドル幅を持ちながらも、NITTOの安全基準をクリアする十分な強度を実現しました。
素材がアルミになったことで、軽量かつ、乗り味もクロモリとは異なるダイレクトなフィーリングに。MTBやクロスバイクのカスタムの第一歩として、劇的な乗りやすさの変化を体感できるハンドルです。
B904 “HiHi-Bar” (クロモリ)
そして、当初のアイデアだったクロモリ製というコンセプトと、NITTOからの提案であったクロスバーを融合させて誕生したのが「hihi-bar」です。
BMXハンドルのようなクロスバーが追加されたことで、見た目のインパクトと、どんなラフなライディングにも耐えうる圧倒的な剛性を手に入れました。ライズ(高さ)はhi-barよりもさらに高い約100mm。クロモリ特有のしなやかな乗り心地と相まって、究極のリラックスポジションを提供してくれます。
一つのアイデアが、予期せぬ課題を経て、特性の異なる2つの素晴らしいプロダクトに昇華した。この開発ストーリーこそ、このハンドルたちの最大の魅力かもしれません。
このハンドルは、なぜこれほどまでに愛されるのか
「hi-bar」と「hihi-bar」が多くのサイクリストに支持される理由は、その普遍的なデザインと懐の深さにあります。
- どんな自転車にも似合う魔法のデザイン: 古いクロモリのMTBはもちろん、最新のグラベルバイク、クロスバイク、シングルスピードまで。不思議なことに、どんな車種に付けてもすんなりと馴染み、その自転車が元々持っていたかのような自然な佇まいを見せてくれます。
- カスタムの幅を広げる汎用性: クランプ径は25.4mmや31.8mmが用意されており、多くのステムに対応します。また、ハンドル幅も十分にあり、カットして自分の肩幅に合わせ込むことも可能です。グリップやブレーキレバーの選択肢も広く、自分だけの一台を作り上げる楽しみを広げてくれます。
- 「楽」がもたらす「楽しさ」: 自転車の楽しみ方はスピードだけではありません。楽な姿勢で走ることで、今まで気づかなかった街の風景や季節の移ろいを感じることができる。このハンドルは、そんな自転車の原点ともいえる「散歩するような楽しさ」を再発見させてくれるのです。
カラーバリエーションと仕上げの美学
現在のカラーバリエーションは、美しいポリッシュ仕上げのシルバーと、どんな車体も引き締めて見せる精悍なブラックが基本です。(hi-barには渋いスチールグレーなども存在します)
特筆すべきは、やはりNITTOならではの仕上げの美しさ。シルバーは、金属の質感を活かした磨き込みが所有する喜びを感じさせてくれます。ブラックも同様に、均一で滑らかな塗装が施されており、その品質の高さは一目見れば分かります。
こうした細部へのこだわりが、製品全体の品格を高め、僕たちのようなモノ好きの心を掴んで離さないのでしょう。
僕のMuddyFoxを変えた、魔法のハンドル
何を隠そう、僕の自転車のルーツはBMXにあります。
だから、こういうアップライトで幅広なハンドルには、どうしても心が躍ってしまうんです。NITTOとBLUE LUGがこのハンドルをリリースした時、「これは事件だ」と本気で思いました。
そして、その想いは今、僕のオールドMTBで最高の形になっています。レストアしたARAYAのMuddyFoxに、試しに「hi-bar」を取り付けてみたんです。
するとどうでしょう。あれほど前傾姿勢で戦闘的だったMTBが、まるで魔法にかかったように、肩の力を抜いてどこまでも走っていけるような、最高にゴキゲンなクルーザーに生まれ変わりました。
その乗り心地が本当に快適で、最近では僕のメインバイクであるEvasionの出番が減ってしまうほど。晴れた日には決まってこのMuddyFoxにまたがり、大阪の街をのんびり流しています。
このハンドルは、ただのパーツ交換ではなく、自転車との新しい関係性を築いてくれる、そんな力を持っているんです。
まとめ:一本のハンドルが繋ぐ、作り手と乗り手の物語
今回は、NITTOとBLUE LUGが生んだ「hi-bar」と「hihi-bar」について、その背景を深く掘り下げてみました。
一本のビンテージハンドルとの出会いから始まり、デザイナーである金子さんの情熱と哲学、そしてNITTOの確かな技術力。
さらに、開発過程で生まれた「強度」という課題を乗り越えるアイデアが、結果として素材とキャラクターの異なる2つの名作を生み出したという事実は、モノづくりの面白さと奥深さを教えてくれます。
自分の愛車にこのハンドルを取り付けたら、いつもの道がどんな風に見えるだろうか。そんな想像をしてみるだけで、なんだかワクワクしてきませんか?
もしあなたが今の乗車姿勢に少しでも疑問を感じていたり、自転車の見た目をガラッと変えてみたいと思っていたりするなら、この物語を持つハンドルを試してみる価値は十分にあります。きっと、新しい自転車の楽しみ方が見つかるはずです。
この記事を読んで、「hi-bar」や「hihi-bar」について感じたことや、実際に使っている方の感想などがあれば、ぜひ下のコメント欄で教えてくださいね。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!