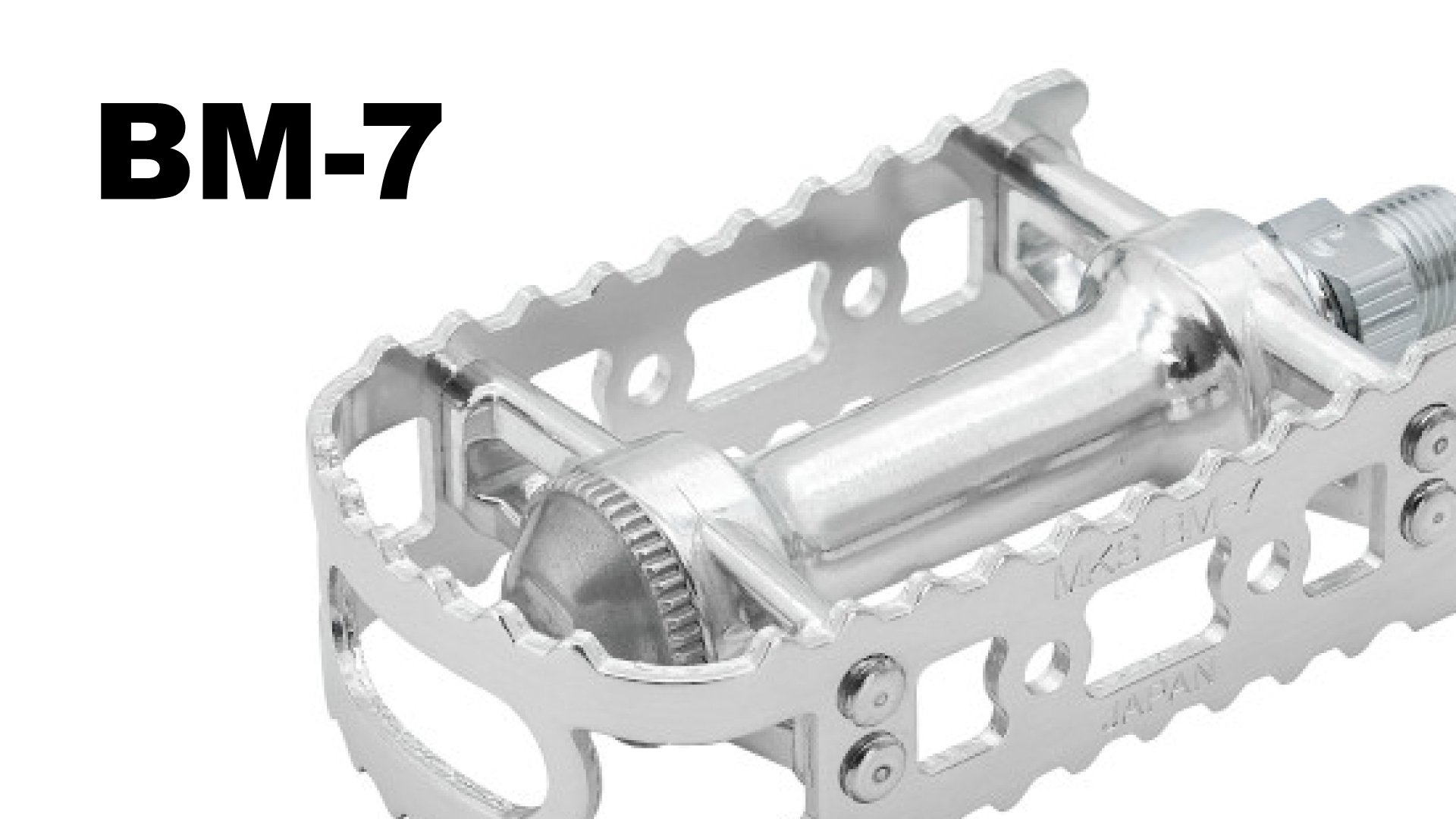足元から、走りは変わる。Crankbrothers Stampペダルが起こした静かな革命
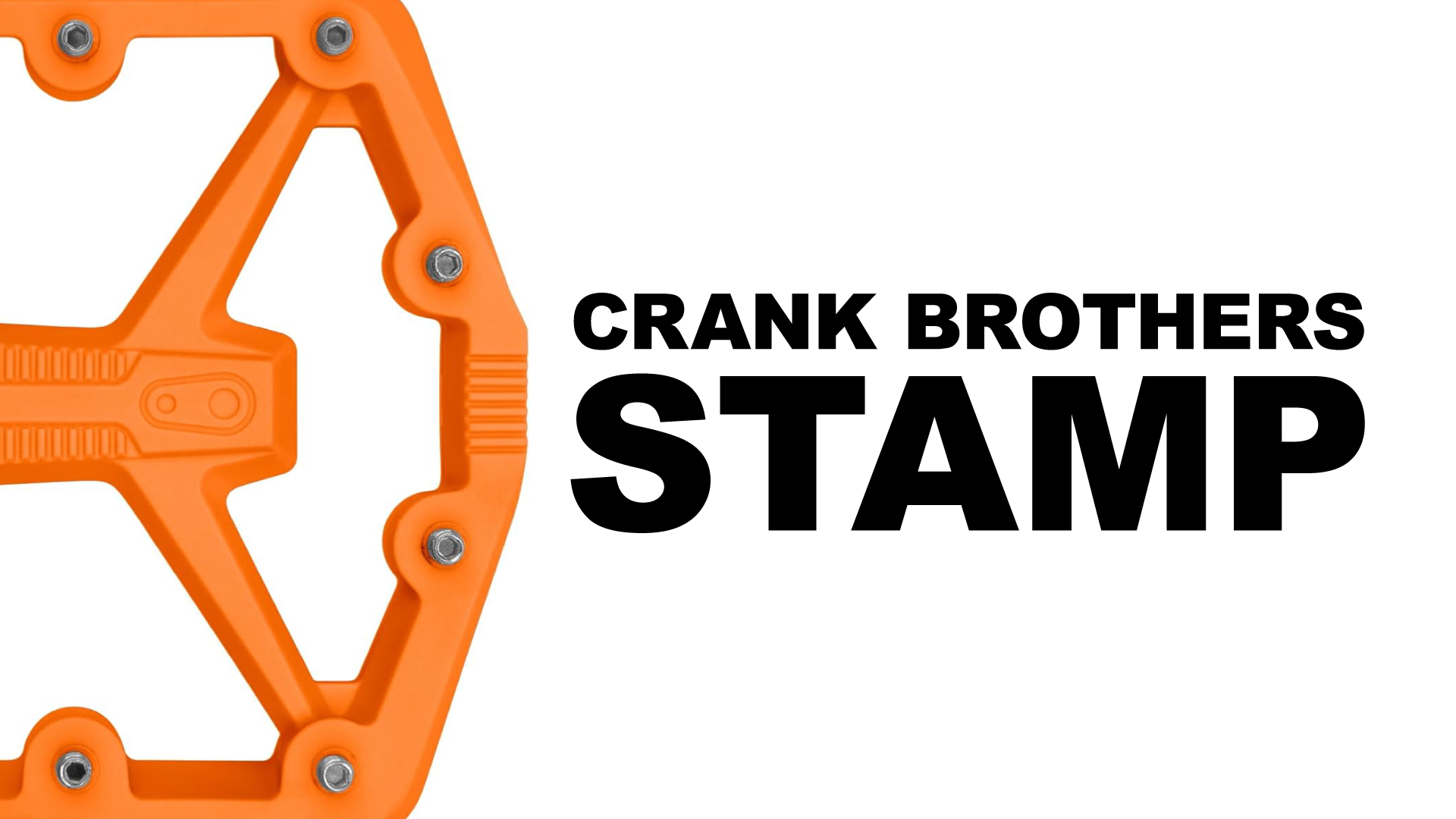
こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕が自転車のパーツの中でも特に「デザインと機能の融合」という点で、いつも注目しているブランドのひとつ、Crankbrothers(クランクブラザーズ)のStamp(スタンプ)シリーズというフラットペダルについて、じっくりとお伝えしようと思います。
単なる「踏むための板」ではない、ペダルというパーツ。ライダーの力を推進力に変える、バイクとの数少ない接点です。だからこそ、ここにはブランドの哲学や作り手の思想が色濃く反映されるんですよね。Stampペダルを知ったとき、僕が感じたのは「ああ、ここまで乗り手のことを考えて作られたペダルがあったのか」という純粋な驚きでした。なぜこのペダルが世界中のMTBライダーから街乗りのサイクリストまで、多くの人々に支持されているのか。その背景にあるストーリーや、プロダクトとしての魅力を、他のどこよりも詳しく掘り下げていきたいと思います。
デザインと機能が生んだ、Crankbrothersの哲学
Crankbrothersというブランドが生まれたのは1997年のこと。カリフォルニア州南部のラグナビーチにある小さなガレージで、二人の創業者によって設立されました。彼らが目指したのは、既存の常識にとらわれず、あらゆる概念や障壁を取り払い、シンプルで美しく、かつ機能的な製品を世に送り出すことでした。
Crankbrothersの名を世に知らしめたのは、泡立て器のような形状の「eggbeater」ペダルに代表される、ミニマルで機能的な製品群でした。彼らの製品に共通しているのは、常識にとられない発想で課題を解決し、それを美しいデザインに落とし込むこと。所有する喜びを感じさせてくれるような、工芸品にも似た佇まいを持っていることです。デザイナーである僕の心が惹かれるのも、まさにその点であり、その哲学がフラットペダルというジャンルでどのように表現されたのかが、今回の主役であるStampシリーズなのです。
なぜStampは生まれたのか?シューズサイズに着目した革新
そんな彼らがフラットペダルの世界に投じた一石が、このStampシリーズです。開発の根底にあったのは、非常にシンプルでありながら、これまで誰も本格的に着手してこなかった問いでした。
「ライダーの足の大きさが違うのに、なぜペダルはワンサイズなんだ?」
そこでCrankbrothersは、トップライダーたちと協力し、膨大なテストを実施。シューズのアウトソール形状とペダルの踏み面の関係を徹底的に分析しました。そうして導き出されたのが、ライダーのシューズサイズに合わせてペダルの大きさを選ぶという、革新的なコンセプトだったのです。具体的には、シューズサイズEU43〜43.5(約27.5cm〜28cm)あたりを境に、それより小さい方向けのSmallと、大きい方向けのLargeという2サイズを展開しました。
このコンセプトのユニークさは、実際に製品を手に取るとより明確にわかります。自転車ショップで他の多くのブランドのペダルと並べてみると、特にLargeサイズは、明らかに一回り、いやそれ以上に大きく設計されていることに驚くはずです。従来の「フリーサイズ」的なペダルがいかに妥協の産物であったかを物語っています。この広大なプラットフォームは、シューズのソールを面でしっかりと支え、これまでにないほどの安定感と安心感をライダーに与えてくれます。コーナーで一度足を外しても、焦らずに踏み直せる。この余裕こそが、Stampペダルがもたらす大きなメリットなのです。
ミニマルなデザインに隠された、徹底的なこだわり
Stampペダルの魅力は、サイズ展開だけではありません。そのミニマルな造形には、ライディング体験を向上させるための工夫が随所に凝らされています。
吸い付くような安定感を生む「コンケーブ形状」
ペダルの踏み面は、中央部が薄く、外周部が厚い「コンケーブ(凹面)形状」になっています。これにより、シューズのソールが自然とペダルの中央に収まり、まるで吸い付くかのような安定感が生まれます。特に荒れた路面を走るときや、コーナリング時のバイクコントロールにおいて、この安定感は絶大な安心につながります。
計算され尽くしたピン配置
グリップの要となるピンは、モデルごとに最適な高さや形状のものが採用され、交換や調整も可能です。片面あたり9〜10本配置されたピンがシューズソールを確実に捉えつつ、過度に食い込みすぎない絶妙なバランスは、ライダーの自由な足の動きも妨げません。
長く使うことを前提とした、信頼性の高い内部構造
ペダルの心臓部であるベアリングにも、Crankbrothersのこだわりが見られます。一般的にベアリングといえば、内部のボールが転がる「ボールベアリング」を想像しますよね。しかし、Stampペダルの多くには、ドイツのIgus(イグス)社製の特殊な**グライドベアリング(滑り軸受)**が採用されています。
これは、金属のボールを使わず、自己潤滑性に優れたポリマー樹脂製のスリーブが軸と直接接して滑ることで、スムーズな回転を生み出す仕組みです。ここで面白いのが、このベアリングの特性です。よく「良いペダルは指で弾くとクルクルと長く回り続ける」と言われますが、Igusベアリングを使ったペダルは、そのような派手な空転はしません。むしろ、少し粘りのあるような、ぬるっとした感触です。
初めて触ると「これ、回転が渋いんじゃないの?」と不安に思うかもしれません。でも、心配は無用です。これはあくまで荷重がかかっていない状態でのこと。実際にバイクに乗ってペダルを踏み込むと、この自己潤滑性ポリマーが真価を発揮し、驚くほどスムーズに、そして抵抗なく回転してくれるんです。
さらに素晴らしいのが、Crankbrothersが「長く使い続けること」を前提に製品を設計している点です。ベアリングやシール、エンドキャップといった消耗部品は「ペダルリフレッシュキット」として販売されており、国内でも安定して流通しています。つまり、もし回転性能が落ちてきても、自分でメンテナンスを行うことで、まるで新品のような性能を取り戻すことができるのです。これは、ペダルを単なる消耗品ではなく、長く付き合えるパートナーとして考えているブランドの姿勢の表れですよね。
足元から個性を主張する。豊富なバリエーション
Stampペダルのもうひとつの大きな魅力は、その豊富なラインナップとカラーバリエーションです。自分のバイクやスタイルに合わせて、最適な一つを選べる楽しさがあります。
ブラックやシルバーといった定番色はもちろん、レッド、ブルー、オレンジ、パープルなど、鮮やかなアルマイトカラーが揃っており、バイクの差し色としてカスタムのアクセントにぴったりです。最近ではアースカラーのような現代的なニュアンスカラーも登場しています。特にクロモリフレームのようなシンプルなバイクには、こうしたパーツのカラーがよく映えますよね。
そのデザイン性の高さから、本来の主戦場であるマウンテンバイクだけでなく、グラベルロードやBMX、そして僕らが楽しむような街乗りのカスタムバイクにも広く取り入れられています。足元に少し色が入るだけで、バイク全体の印象がガラリと変わる。そんなカスタムの醍醐味を味わえるパーツです。
STAMPシリーズのラインナップ
Stampシリーズは、素材や内部構造の違いによっていくつかのグレードに分かれています。代表的なモデルをいくつかご紹介します。
Stamp 1
コストパフォーマンスに優れた強化コンポジット(樹脂)ボディのモデル。軽量で、カラーバリエーションも非常に豊富。街乗りからトレイルライドの入門用として最適です。
Stamp 3
堅牢なアルミ合金(アルミニウム)ボディを採用したモデル。よりタフなライディングにも対応する耐久性が魅力です。
Stamp 7
Stampシリーズの中核をなすハイエンドモデル。鍛造アルミ製の薄く軽量なボディと、高品質な内部パーツで、最高のパフォーマンスを発揮します。プロライダーのフィードバックが色濃く反映された、まさにレースグレードの逸品です。
Stamp 11
アクスルシャフト(軸)に軽量で高剛性なチタンを採用した、シリーズ最上位のフラッグシップモデル。究極の軽さと性能を求めるライダーのための、まさに”最終兵器”と言えるペダルです。
まとめ:Stampペダルが変える、ライディング体験
今回は、CrankbrothersのStampペダルについて、その背景からプロダクトの魅力までを掘り下げてきました。
Stampペダルが多くのライダーに支持される理由は、単に高性能だから、というだけではありません。そこには「すべてのライダーに最適なインターフェースを提供する」という明確な哲学があります。自分の足に合ったシューズを選ぶように、自分の足に合ったペダルを選ぶ。広大なプラットフォームがもたらす安心感は、まさにその哲学の賜物です。
そして、その内部構造に目を向ければ、Igusベアリングのように実際のライディングでの信頼性を重視したパーツを選び、さらに補修パーツを供給することで一つの製品を長く使えるように配慮する、実直で誠実なブランドの姿勢が見えてきます。
それは、バイクとライダーの繋がりを、より深く、より確かなものにしてくれるパーツです。もしあなたが今、ペダル選びに悩んでいたり、自分のバイクの走りをもう一段階上のレベルに引き上げたいと考えているなら、選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたのライディング体験を足元から変えてくれるはずです。
この記事が、あなたのペダル選びの参考になれば嬉しいです。皆さんはどんなペダルを使っていますか?ぜひコメントで教えてくださいね。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!