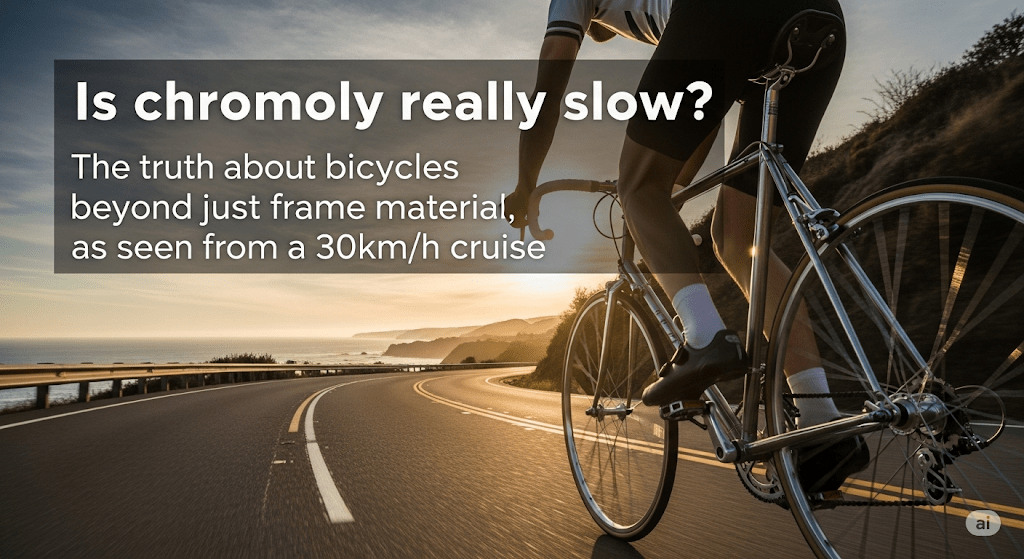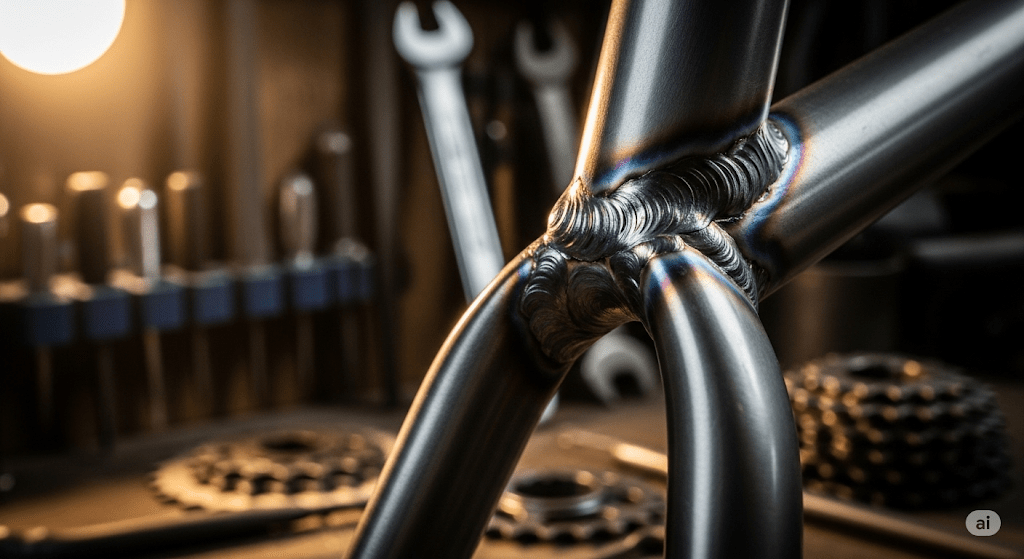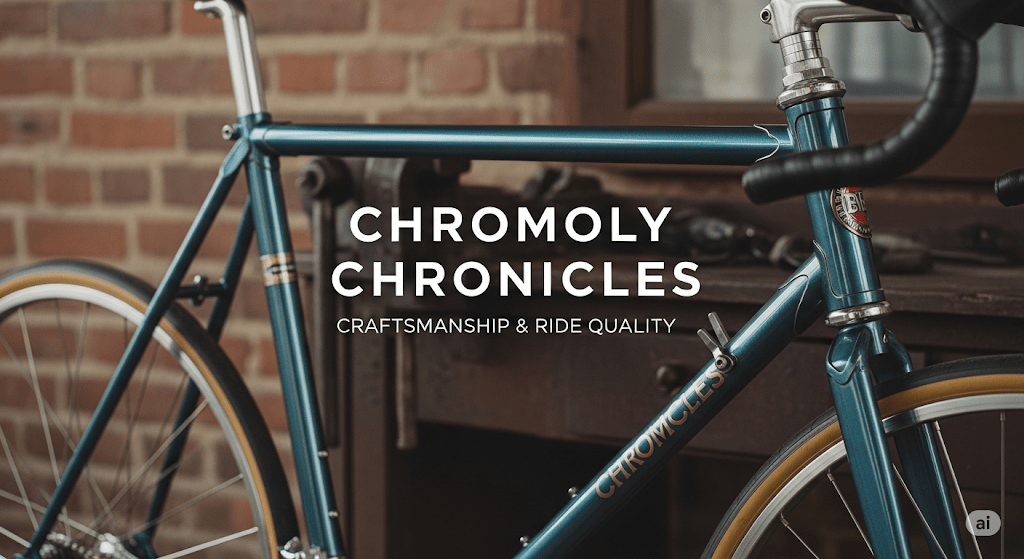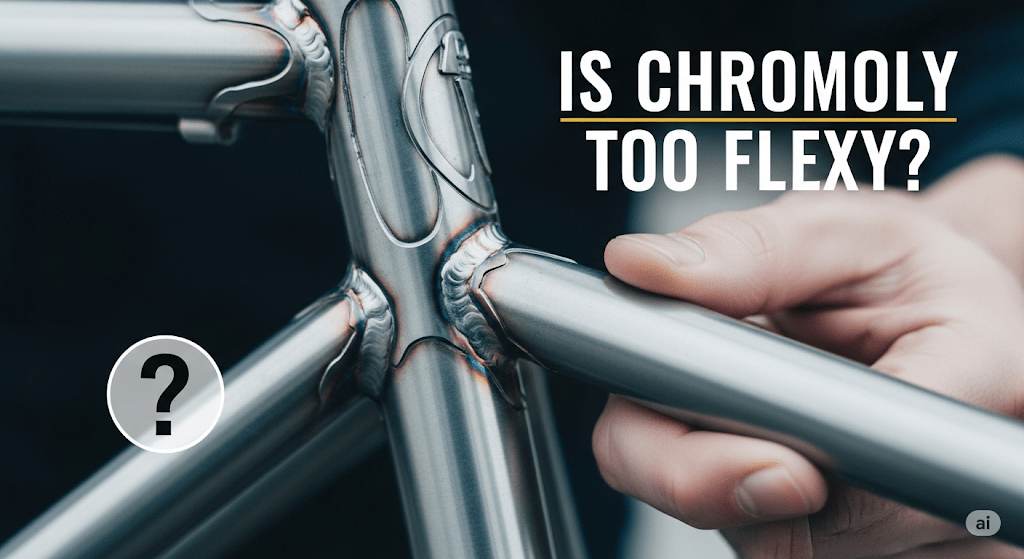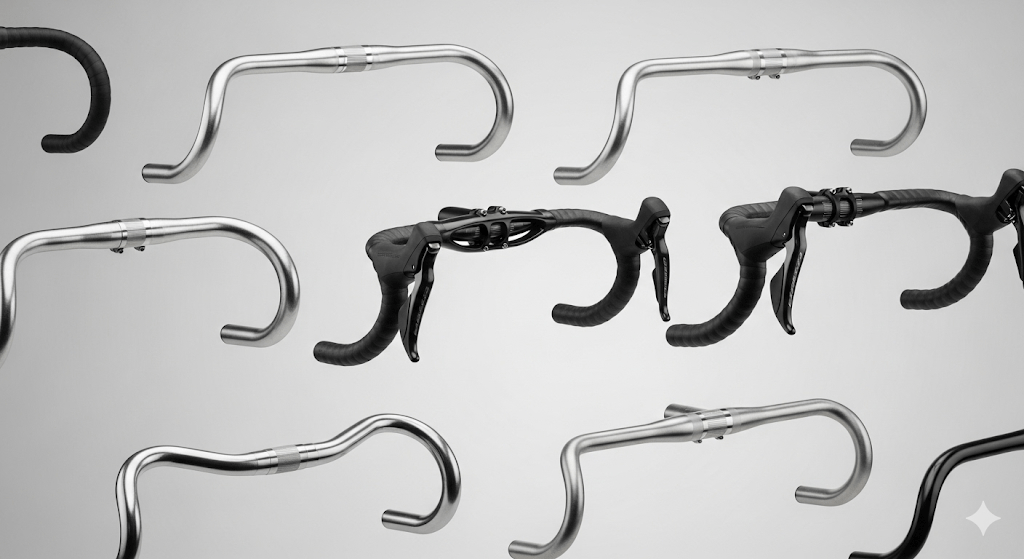クロモリでヒルクライムは無謀?重量差から考える、キツさと楽しみ方の再発見。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。
先日、僕がブログにアップした「クロモリで30キロ巡航は可能か?」という記事が、思いのほか多くの反響をいただきました。僕と同じように、「クロモリでどこまでやれるのか?」という疑問を持っている方がたくさんいらっしゃるんだな、と改めて感じています。
そうなると次に気になるのは、「じゃあ平地だけじゃなくて、坂道はどうなんだろう?」という話ですよね。今回は、そんな皆さんの疑問に答えるべく、自転車乗りなら誰もが一度は耳にする、ちょっとした都市伝説に僕なりの視点で挑んでみようと思います。
それは、「クロモリは重いから、坂道は無理」という、あの根強い先入観についてです。
特に、カーボンフレームの軽快なロードバイクが主流の今、クロモリの自転車に乗っていると、「それだと坂は大変でしょう?」と聞かれることが少なくありません。確かに、見た目のゴツさや、持った時のずっしりとした手応えは、どうしてもそう思わせてしまいますよね。
でも、本当にそうでしょうか?僕の結論から先に言うと、「ヒルクライムのしんどさは、フレームの重さとは実はあんまり関係ない」んです。
今回は、このクロモリフレームとヒルクライムの真実について、僕自身の体験も交えながら、深く掘り下げていきたいと思います。
クロモリ vs カーボン:重量の真実
まず、クロモリフレームとカーボンフレームの重量差について、考えてみましょう。
「カーボンは軽い」「クロモリは重い」というのは事実ですが、その差は一体どれくらいだと思いますか?
最新の軽量カーボンフレームと、一般的なクロモリフレームを比べても、その重量差は実は1〜2キロ程度です。もちろん、この差は大きいと思うかもしれません。でも、考えてみてください。超ハイスペックなライトウェイトフレームでもない限り、4キロも差があることはなかなかないんじゃないかと思います。たった1〜2キロの差なんて、僕たちの体重が少し増えたり減ったりするだけで簡単にひっくり返ってしまいます。
ライド中にペットボトルを1本(約500g)余分に持っているだけで、すでに半分近い差を埋めてしまいますし、水分補給や食事の内容、さらには荷物の量で簡単に変わってしまうレベルなんです。
自転車の世界では、1秒1秒を争うプロのレースでは、この1〜2キロが勝敗を分ける重要な要素になります。でも、僕たちが楽しむ、日曜日のサイクリングやツーリング、ましてやタイムを気にしないヒルクライムであれば、この重量差を気にすることは、正直なところ、あまり意味がありません。
ヒルクライムのしんどさの正体:フレーム素材ではない
では、ヒルクライムのしんどさの正体は一体何なのでしょうか?僕の経験から言わせてもらうと、それはフレームの重さではなく、「身体」と「漕ぎ方」に依存しています。
- ギヤ比: 適切なギヤ比を選べているかどうかは、ヒルクライムの難易度を劇的に変えます。軽めのギヤでクルクルとペダルを回すことができれば、重いフレームでも楽に登ることができます。逆に、重いギヤで力任せに登ろうとすると、どんなに軽いカーボンフレームでも、すぐに足が売り切れてしまいます。トルクをかけて踏み抜くのではなく、ケイデンス(ペダルの回転数)を維持することが、長い坂を登り切るための鍵なんです。
- 漕ぎ方(ペダリング): いかに効率よくペダルを回せるかという技術も、ヒルクライムには欠かせません。ただ脚の力だけで踏み込むのではなく、まるでダンスをするように、全身を使ってペダルを踏み抜くことが重要です。上半身を使い、体幹を意識して、滑らかに力を伝えることができれば、無駄なエネルギーを使わずに、重いフレームでも疲れにくくなります。むしろ、振り子として触れる重量があるぶん、体重移動は筋肉に依存せずスムーズになり、体重でペダルを踏み抜く連続の動作をしやすくなります。
- 身体(乗り手のコンディション): そして何より、僕たち自身の体力が最も大きな要素です。体重、筋肉量、心肺機能、その日の体調、さらには「絶対に登り切ってやる」という強い気持ち。これらが、フレームの重量差よりもはるかに、ヒルクライムの難易度を左右します。
いや、そもそも論として、何をやっても坂ってしんどいもんなんです(笑)。
僕のヒルクライム体験談:Crust Evasionと坂道
僕の愛車であるCrust Evasionは、クロモリフレームに太いタイヤを履いた、どちらかというと重量級のバイクです。ヒルクライムに特化したバイクとは、お世辞にも言えません。
でも、僕は大阪の街から少し足を伸ばして、山道へと向かうのが大好きです。もちろん、坂を登るのはしんどいです(笑)。でも、それは、Crustに乗るからではなく、坂道そのものがしんどいんです。
それでも僕は、この重いバイクで坂を登るのが好きです。なぜなら、クロモリ特有の「粘り」と「しなやかさ」が、上り坂での疲労を和らげてくれるからです。硬いカーボンフレームのように路面からの振動をダイレクトに拾うのではなく、クロモリは路面の凹凸を優しくいなしてくれるので、体に伝わる衝撃が少ないんです。
そして何より、重いフレームで登るからこそ、下りの安定感がたまらない。路面に吸い付くような感覚で、安心してグングンと下っていくことができます。僕にとって、自転車の楽しみは、登り切った後の下りまで含めて一つのライドなんです。
ただ、ここで一つ注意しておきたいのは、怖いのはむしろ下りの方だということ。
クロモリの自転車は、ビンテージ車など古いモデルだと昔ながらのリムブレーキを搭載しているものが多いです。最近のクロモリフレームはディスクブレーキに対応しているものも増えてきていますが、リムブレーキだと雨や露でリムが濡れると、途端に制動力が落ちてしまうことがあります。
僕も以前所有していたMASIのクロモリロードで、峠を降りていた時に突然の雨に降られ、ブレーキがほとんど効かなくなったことがあって、その時は本当に冷や汗をかきました。あの恐怖は今でも忘れられません。
だからこそ、もしこれからクロモリの自転車を迎え入れようと考えているなら、信頼性の高いブレーキ、特にディスクブレーキのモデルを選ぶことをおすすめします。そうすれば、安心して登りも下りも楽しむことができます。
まとめ:大切なのは「イケる」という気持ち
「イケんのか?クロモリでヒルクライム!」という問いへの僕の答えは、こうです。
「もちろん、イケます!」
確かに、カーボンフレームと比べれば重量のハンデはあります。でも、それはあくまで「性能」の差であって、僕たちの「楽しみ」を奪うものではありません。
大切なのは、フレームの素材が何であるかではなく、その自転車でどこへ行きたいか、そしていかにその旅を楽しむか、ということです。
想像してみてください。みんながカーボンフレームで必死にタイムを競って登っていく横を、あなたはクロモリフレームの愛車で、その景色を楽しみながら、淡々と、そして颯爽と登っていく自分の姿を。
重いクロモリフレームで挑むヒルクライムには、軽いフレームで得られるスピードとは違う、自分自身の力で道を切り拓いていくような、深い達成感があります。
自転車との旅を、どんなフレームで楽しむか。それは、自分自身の人生を、どんなスタイルで歩むか、ということなのかもしれません。
皆さんは、どんなフレームで坂道に挑んでいますか?ぜひ、コメントであなたの愛車やヒルクライムの思い出を教えてほしいです。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!
Hello, I’m Hiroyasu. I’m a designer in my 40s who is still riding my bike through the streets of Osaka. Thank you so much to all of you who always read my blog. The other day, an article I posted on my blog titled “Is it Possible to Cruise at 30km/h on a Chromoly Bike?” received an unexpectedly large response. It made me realize once again that many people, just like me, have the question, “How far can I go with chromoly?” That brings us to the next question: “Well, what about hills, not just on flat ground?” This time, to answer that question, I’d like to challenge a bit of an urban legend that every cyclist has heard at least once, from my own perspective. That is the persistent preconception that “chromoly is heavy, so it’s impossible to ride uphill.” Especially now that lightweight carbon-frame road bikes are mainstream, I’m often asked, “Isn’t it tough on hills with that?” when I’m riding my chromoly bike. Indeed, its bulky appearance and solid feel when you lift it naturally make people think that. But is that really true? To give you my conclusion first, “The difficulty of a hill climb actually has little to do with the weight of the frame.” This time, I’d like to delve deep into the truth about chromoly frames and hill climbing, based on my own experiences.
Chromoly vs. Carbon: The Truth About Weight
First, let’s consider the weight difference between a chromoly frame and a carbon frame. While it’s a fact that “carbon is light” and “chromoly is heavy,” how big do you think that difference actually is? Even when comparing the latest lightweight carbon frame with a standard chromoly frame, the weight difference is actually only about 1 to 2 kilograms. Of course, you might think this is a big difference. But think about it. Unless it’s a super high-spec lightweight frame, I don’t think there’s often a 4-kilogram difference. A difference of just 1 to 2 kilograms can easily be overturned by a slight increase or decrease in our own body weight. Just carrying one extra plastic bottle of water (about 500g) on a ride already closes almost half the gap, and the difference is easily changed by hydration, the contents of your meals, and even the amount of luggage you’re carrying. In the world of cycling, where professionals race for every second, this 1 to 2 kilograms is an important factor that can decide victory or defeat. But for the Sunday cycling, touring, or even hill climbing without worrying about time that we enjoy, worrying about this weight difference is, to be honest, not very meaningful.
The True Nature of the Difficulty in Hill Climbing: It’s Not the Frame Material
So, what is the true nature of the difficulty in hill climbing? From my experience, it depends on the “body” and the “pedaling technique,” not the weight of the frame.
- Gear Ratio: Choosing the right gear ratio can dramatically change the difficulty of a hill climb. If you can pedal smoothly and spin your legs in a light gear, you can climb easily even with a heavy frame. Conversely, if you try to climb with brute force in a heavy gear, your legs will be shot in no time, no matter how light your carbon frame is. The key to climbing a long hill is not to push through with torque, but to maintain a high cadence (pedal rotations per minute).
- Pedaling Technique: The technique of how to pedal efficiently is also essential for hill climbing. It’s important not to just push down with leg strength, but to use your entire body to push through the pedals, as if you’re dancing. By using your upper body and engaging your core to transmit power smoothly, you can climb with a heavy frame without getting tired, as you’re not using unnecessary energy. In fact, because there is weight that can act as a pendulum, weight transfer becomes smoother without relying on muscles, making it easier to perform the continuous motion of pushing down on the pedals with your body weight.
- Body (Rider’s Condition): And most importantly, our own physical fitness is the biggest factor. Body weight, muscle mass, cardiovascular function, your condition on that day, and even a strong desire to “definitely make it to the top.” These factors influence the difficulty of a hill climb far more than the weight difference of the frame. Actually, as a fundamental point, climbing a hill is just tough, no matter what you do (laughs).
My Hill Climbing Story: The Crust Evasion and Hills
My beloved Crust Evasion is a relatively heavy bike with a chromoly frame and wide tires. It’s not a bike that’s specifically designed for hill climbing, to be honest. But I love extending my ride from the streets of Osaka and heading into the mountains. Of course, climbing hills is tough (laughs). But that’s not because I’m on the Crust, it’s because the hills themselves are tough. Even so, I love climbing hills on this heavy bike. That’s because the unique “tenacity” and “flexibility” of chromoly frames ease fatigue on ascents. Instead of picking up road vibrations directly like a stiff carbon frame, chromoly gently soaks up road bumps, so there’s less impact transmitted to your body. And most of all, because I climb on a heavy frame, the stability on the descent is simply unbeatable. The feeling of being stuck to the road lets me descend with confidence and speed. For me, the enjoyment of cycling includes the descent after a climb, all as one ride. However, one thing I want to point out here is that the descent is actually the scarier part. Many older chromoly bikes, like vintage models, are equipped with traditional rim brakes. While an increasing number of recent chromoly frames support disc brakes, with rim brakes, if the rim gets wet from rain or dew, the braking power can suddenly drop. When I was riding my old MASI chromoly road bike, I was going down a pass when a sudden rainstorm hit, and my brakes barely worked. I broke out in a cold sweat that day. I’ll never forget that fear. That’s why, if you’re thinking about getting a chromoly bike, I highly recommend choosing a model with reliable brakes, especially disc brakes. That way, you can enjoy both the climb and the descent with peace of mind.
Conclusion: What Matters is the Feeling of “I Can Do It”
My answer to the question, “Can I do it? Hill climbing on a chromoly bike!” is this: “Of course, you can!” Certainly, there’s a weight handicap compared to a carbon frame. But that’s just a difference in “performance,” and it doesn’t take away from our “enjoyment.” What’s important isn’t what the frame is made of, but where you want to go on that bike, and how much you enjoy the journey. Imagine it. While everyone else is desperately racing against the clock on their carbon frames, you are riding your beloved chromoly bike, enjoying the scenery, and climbing steadily and elegantly. Challenging a hill climb on a heavy chromoly frame gives you a deep sense of accomplishment, like you’re paving your own way with your own strength, which is different from the speed you get from a light frame. What kind of frame you choose to enjoy your journey on a bike with… perhaps that’s a reflection of what style you choose to walk through your own life. What kind of frame do you challenge hills with? Please share your bike and hill climbing memories in the comments! Well then, see you in the next article! This was Hiroyasu!
こんな記事も読まれています。