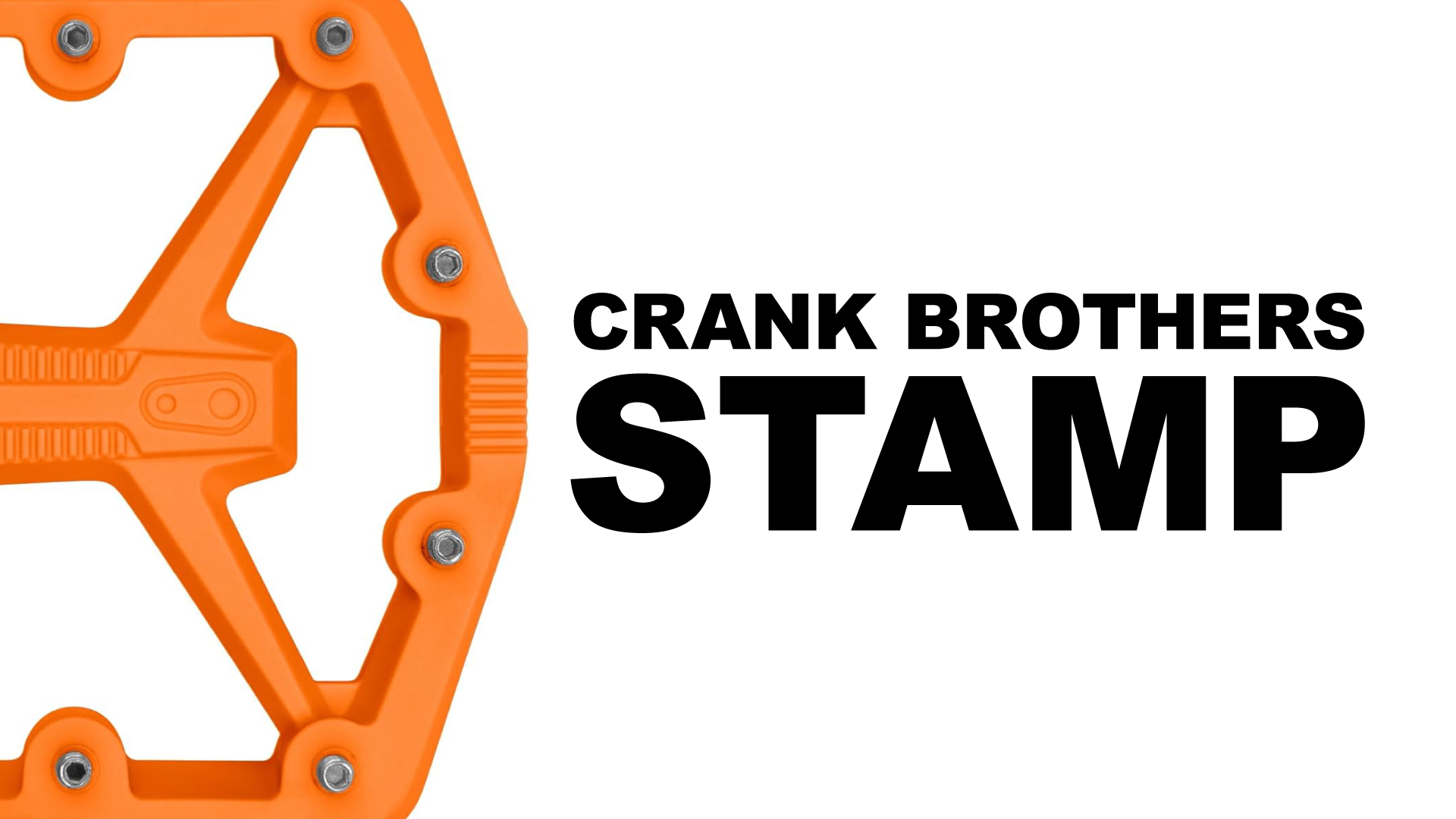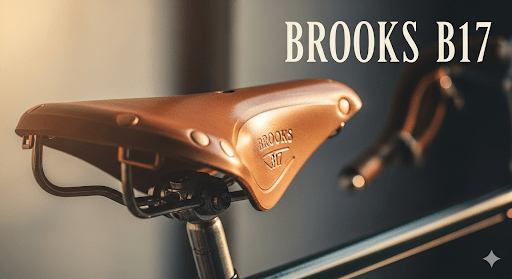クロモリ愛好家が語る、BROOKS TEAM PROの真価。その歴史と哲学に迫る

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。
さて、今回は自転車のパーツの中でも、特に語りがいのある逸品、BROOKSの「TEAM PRO」についてのお伝えしたいと思います。このサドル、ただのパーツじゃないんです。BROOKSというブランドが持つ長い歴史と、職人たちの哲学がぎゅっと詰まった、まさに「物語」を持ったプロダクト。
僕自身、長年クロモリのバイクを組む上で、BROOKSのサドルには特別な魅力を感じてきました。中でもTEAM PROは、その独特な佇まいと、使い込むほどに変化する表情がたまらないんですよね。今回は、TEAM PROがなぜこれほどまでに多くのサイクリストに愛され続けるのか、その背景にある深いストーリーを掘り下げていきたいと思います。他のどのブログやホームページよりも、BROOKSのTEAM PROというプロダクトの真髄に迫っていきますので、最後までお付き合いください。
BROOKSというブランドの揺るぎない哲学
BROOKSの歴史は、1866年まで遡ります。もともとは馬具メーカーとして創業したJ.B. Brooks & Co.が、1882年に自転車用のサドルを開発したことから、その伝説は始まりました。
当時、レザーサドルはまだ普及しておらず、自転車の座面は硬い木材や鉄でできていたそうです。そんな中、快適性を追求し、馬具製造で培った革加工の技術を活かして生まれたのが、BROOKSのレザーサドルでした。
創業者のジョン・ボルトビー・ブルックスは、単なる機能性だけでなく、職人の手仕事と素材への深い敬意を大切にしました。この哲学は、150年以上の時を経た今も、ブランドのDNAとして受け継がれています。サドル一つひとつが熟練の職人の手によって作られ、厳しい品質基準をクリアしたものだけが世に送り出される。TEAM PROもまた、このクラフトマンシップの象徴と言えるでしょう。
TEAM PROが持つコンセプトと歴史
TEAM PROは、BROOKSのサドルの中でも特にロードレースやトラック競技で使われることを想定して開発されました。その名の通り「プロチーム」が使用するにふさわしい、最高のパフォーマンスと耐久性を兼ね備えたサドルとして生み出されたのです。
開発されたのは比較的古く、具体的な年代は資料によってばらつきがありますが、クラシックなロードバイクの黄金期を支えてきたモデルの一つであることは間違いありません。特徴的なのは、その流線型の形状。BROOKSの他のモデル、例えば「B17」のようなツーリング向けサドルと比較すると、TEAM PROはより細身で、前傾姿勢でのペダリングを妨げないように設計された結果です。
また、サドル後部にある大きな銅製リベットも、TEAM PROの象徴的なデザインです。これは単なる装飾ではなく、革をフレームにしっかりと固定するための重要な役割を果たしています。このリベットが打ち込まれたデザインは、無骨でありながらも、どこかエレガントさを感じさせます。
BROOKS TEAM PROとSwift、その共通点と違い
BROOKSのレザーサドルを語る上で、**「Swift」**というモデルも外せません。もしあなたが「TEAM PROとSwift、どちらにしよう?」と悩んでいるなら、ぜひ知ってほしいことがあります。
ぱっと見の印象は非常に似ています。細身のフォルム、そして流れるような美しいライン。両モデルとも、手打ちの銅製リベットが使われているというクラフトマンシップの共通点があります。しかし、両者には明確な違いがあるんです。
【共通点】
- プロフェッショナルな用途を想定したデザイン: どちらもレーシングサドルとして開発されており、空気抵抗の軽減やペダリングのしやすさを考慮した形状をしています。
- エイジングの楽しみ: 天然の革を使用しているため、使い込むほどに自分の体に馴染み、独特の風合いが増していく点は共通の魅力です。
- 手打ちの銅製リベット: どちらも熟練の職人によって、大型の銅製リベットが手打ちされています。これが、サドルの顔とも言えるアイコニックなデザインになっています。
【違い】
- 革の厚みと剛性: TEAM PROは革が厚く、非常に硬質です。そのため、体に馴染むまでには時間と乗り込みが必要になりますが、一度馴染めば揺るぎない安定感と耐久性を発揮します。一方、SwiftはTEAM PROに比べて革が薄く、しなやかです。比較的早く体に馴染みやすいという特性があります。
- デザインの細部: TEAM PROは、無骨なまでにシンプルでクラシックなデザインです。対してSwiftは、サイドの革の端を薄く削り(ハンドスキビング)、そこから下のスエード部分が見えるように加工されており、より繊細で現代的な印象を受けます。
つまり、TEAM PROは「じっくりと時間をかけて育てる、一生もののサドル」。対して、**Swiftは「比較的早く体にフィットし、現代的なデザインも取り入れたサドル」**と言えるでしょう。どちらを選ぶかは、あなたの自転車との付き合い方にかかっています。
なぜ多くのサイクリストに選ばれるのか
TEAM PROが多くのサイクリストに愛されている理由は、いくつかあります。
まず一つは、「育てていく楽しみ」があること。天然の革を使っているため、使い始めは硬く、お尻に馴染むまでには少し時間がかかります。しかし、乗り込むうちに徐々に自分の骨格にフィットしていき、唯一無二の「自分のサドル」へと変化していきます。このエイジングのプロセスこそが、デジタル化が進んだ現代において、モノを大切に使う喜びを再認識させてくれるのです。
次に、その耐久性です。適切なメンテナンス(オイルアップなど)を施せば、一生ものとして使い続けることができます。革が持つ強靭さと、職人による丁寧な作りが、長期間にわたる使用を可能にしています。
そして最後に、その普遍的なデザインです。クラシックなクロモリフレームにはもちろんのこと、現代のバイクに合わせても、その存在感が際立ちます。機能性だけでなく、バイク全体のスタイルを格上げする「デザインパーツ」としての価値も、TEAM PROにはあるのです。
TEAM PROを代表するプロダクト
TEAM PRO CLASSIC
TEAM PROの基本となるモデルです。このモデルは、硬質で耐久性の高い革と、大きな銅製のリベットが特徴的です。ブラック、ハニー、ブラウンといったクラシックなカラーバリエーションが主流で、どんなバイクにも馴染みやすい普遍的なデザインをしています。
TEAM PRO CHROME
こちらは、ステンレス製のレールと銅製のリベットを組み合わせたモデルです。CLASSICに比べて、より光沢のあるクロームメッキのレールが特徴で、カスタムバイクのアクセントとして存在感を発揮します。
TEAM PRO COPPER
銅メッキのレールが特徴的なモデルです。銅は時間とともに独特の風合いに変化していくため、革のエイジングとともに、バイク全体に深みを与えてくれます。細部までこだわりたいライダーに人気のモデルです。
どのようなカスタムに合うパーツなのか
BROOKS TEAM PROは、様々なカスタムバイクに合わせることができます。
- クラシックなロードバイク、ランドナー:もともとレース向けに開発されたモデルであるため、クラシックなロードバイクやツーリング向けのランドナーに合わせると、その雰囲気を一層引き立てます。
- グラベルロード、バイクパッキングバイク:TEAM PROが持つ耐久性と、使い込むほどに馴染む特性は、長距離を走るグラベルバイクにもぴったりです。バイク全体に重厚感とクラフトマンシップの雰囲気を加えることができます。
- シングルスピード、ピストバイク:シンプルでミニマルなデザインのピストバイクに合わせると、サドルが持つ存在感が際立ち、バイク全体のデザインを引き締めてくれます。
まとめ
BROOKS TEAM PROは、単なる自転車のサドルではありません。それは、150年以上にわたるBROOKSのクラフトマンシップと、時代を超えて受け継がれるデザイン哲学が凝縮された「作品」です。
使い始めは少し硬く、乗り心地に違和感を覚えるかもしれません。しかし、この「硬さ」こそが、TEAM PROが持つ特別な魅力です。自分の体と対話しながら、時間をかけて革を育て、形を馴染ませていく。そのプロセスは、まるで自転車と一緒に旅をするような感覚です。ペダルを漕いだ分だけ、汗を流した分だけ、サドルがあなたの体の一部になっていく。この「育てる」というプロセスは、大量生産・大量消費の時代に忘れられがちな、モノへの愛着と向き合う貴重な機会を与えてくれます。
そして、その堅牢さは、まさに一生もの。適切なメンテナンスを施せば、親子二代にわたって使い続けることだって可能です。使い込まれた革が放つ独特の光沢と風合いは、そのサドルが辿ってきた道のりを物語ってくれます。
クロモリのバイクを組む上で、機能性だけでなく、ストーリーや背景にまでこだわりたい。そんなライダーにとって、BROOKS TEAM PROは最高の選択肢の一つになるはずです。もし今、新しいサドルを探している方がいらっしゃれば、ぜひTEAM PROを手に取って、その重みと革の質感を確かめてみてください。きっと、あなたの自転車ライフをより豊かなものにしてくれるはずです。
BROOKS TEAM PROについて、皆さんの感想や、もし使っている方がいれば「ここがいいよ!」というポイントなど、コメントでぜひ教えてください!
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!