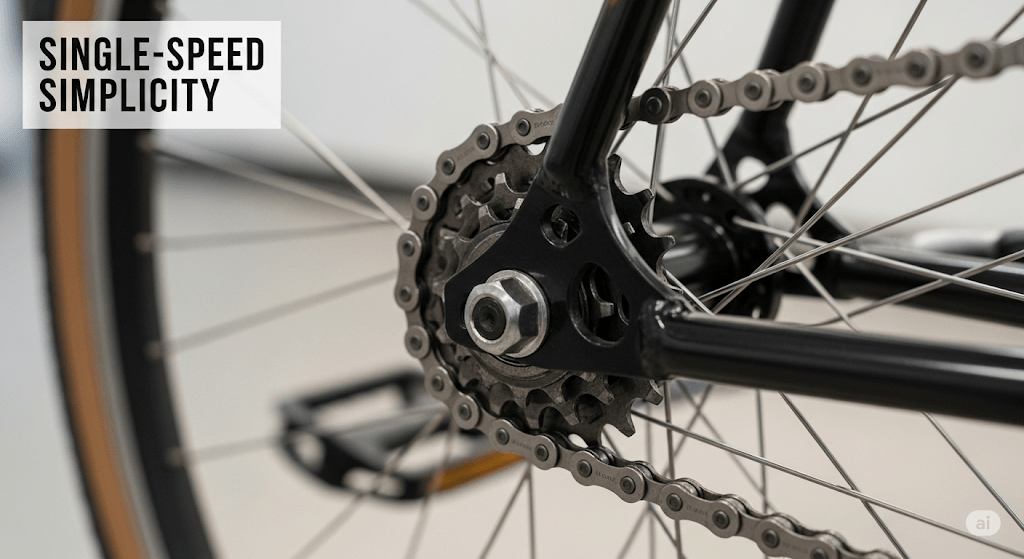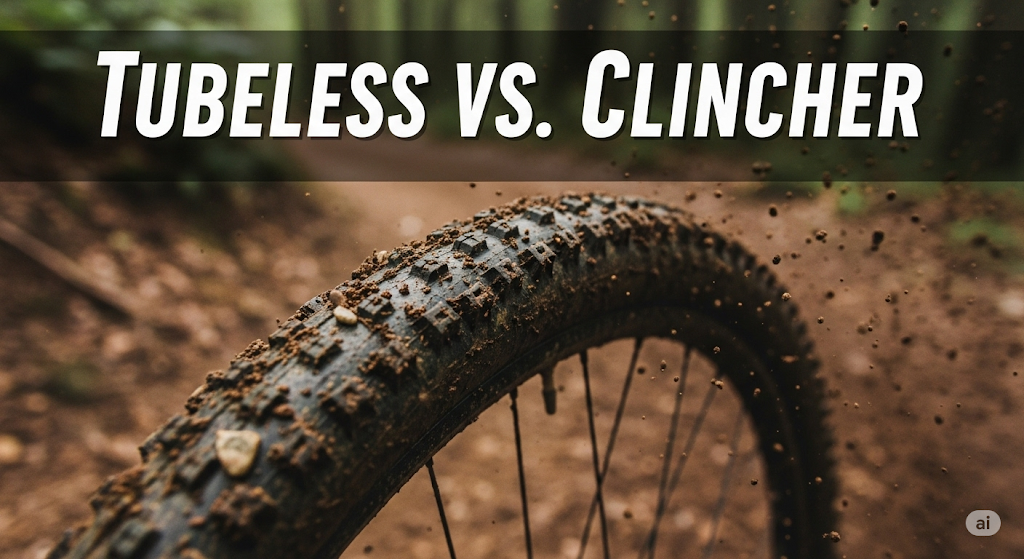軽いクロモリフレームを探せ!現行手に入る中での「軽量」クロモリフレームを集めました!

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、クロモリフレームの自転車が好きな僕たちが、心のどこかでずっと気になっている「重さ」というテーマに、真正面から向き合ってみたいと思います。
「クロモリは重さを気にして乗るもんじゃないよ」
そんな声が聞こえてきそうです。ええ、ええ、僕も心の底からそう思います。あのしなやかな乗り心地、細身のパイプが織りなす普遍的なデザインの美しさ。それこそがクロモリの魅力であり、多少の重量増なんて気にならない…はず。
はず、なんですが!
やっぱり気になってしまうのが自転車乗りの性(さが)というものじゃないでしょうか。特に、ヒルクライムで息が上がっている時、ふと「このバイクがもう少し軽かったら…」なんて思ってしまう瞬間、ありませんか?
カーボンやアルミの最新鋭機とスペックで張り合うつもりは毛頭ない。でも、伝統的な素材であるクロモリが、現代の技術と哲学でどこまで「軽く」なれるのか。その可能性を探求するのは、自転車好きとして、そしてモノづくりに関わるデザイナーとして、めちゃくちゃワクワクするテーマなんです。
今回は、そんな「軽さ」という新たな視点で、現在手に入れることができるクロモリロードフレームの世界を深掘りしていきたいと思います。
なぜクロモリは「重い」と言われるのか?
本題に入る前に、少しだけおさらいです。クロモリ、すなわちクロムモリブデン鋼は鉄をベースにした合金です。当然、比重で言えばアルミやチタン、そしてカーボンファイバーよりも重たい素材です。
しかし、素材の強度の高さからパイプを薄く加工することができ、結果としてフレーム全体の重量を抑えることが可能になります。特に「ダブルバテッド」や「トリプルバテッド」といった、力のかかる両端は厚く、中央部分を薄くする加工技術が進化し、クロモリフレームは劇的に進化しました。
それでも、やはり素材そのものの特性上、絶対的な軽さでは他の素材に軍配が上がることが多い。これが「クロモリ=重い」というイメージの正体です。
でも、本当にそうでしょうか?現代の技術で作られたクロモリフレームは、僕たちの想像をはるかに超える軽さと走りを提供してくれるんです。
「軽さ」は走りにどう影響する?
フレームの重量は、ただの数字ではありません。それはバイクの性格、つまり「乗り味」に直結します。
軽いフレームは、漕ぎ出しの軽快さや、坂道を登る際の負担軽減に大きく貢献します。ペダルを踏み込んだ力が、よりダイレクトに推進力に変わる感覚は、一度味わうと病みつきになるかもしれません。いわゆる「ヒラヒラ感」と表現されるような、軽快なダンシング(立ち漕ぎ)も軽量フレームの得意分野です。
一方で、過度な軽量化は、クロモリ本来の魅力である「しなやかさ」や「乗り心地の良さ」をスポイルしてしまう可能性も秘めています。フレームが軽くなることで、路面からの振動を拾いやすくなったり、高速走行時の安定感が少し失われたりすることもあります。
つまり、軽さと乗り心地はトレードオフの関係にあることが多いのです。どのバランスを最適とするか。そこにビルダーやメーカーの哲学が現れるわけですね。
注目すべき軽量クロモリブランド
それでは、いよいよ本題です。具体的にどんなフレームがあるのか、見ていきましょう。
まずは比較の基準として、多くのサイクリストに愛されているSURLY(サーリー)のCross-Checkを挙げたいと思います。頑丈で懐が深く、まさに「ザ・クロモリ」といったこの名作フレームは、フレーム単体で約2.2kg、フォークが約1.0kgで、合わせておよそ3.2kgになります。これを一つの基準として頭に入れておいてください。
日本が誇るオーダーフレームの雄 Panasonic
パナソニックと聞くと家電を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、自転車の世界では、世界的なレースでも活躍した歴史を持つ、日本を代表するブランドの一つです。特に「POS(パナソニック・オーダー・システム)」は、熟練の職人たちが国内の自社工場で一本一本フレームをビルドするという、非常に贅沢なシステム。僕たちユーザーの体型や好みに合わせて、ミリ単位でジオメトリーを調整してくれます。
英国の伝統と革新 Raleigh
130年以上の歴史を持つイギリスの老舗、ラレー。伝統を重んじるブランドでありながら、その歩みを止めることはありません。現代のロードバイクに求められるスペック、例えばディスクブレーキや電動コンポーネントといった最新技術を、クロモリという伝統的な素材にどう融合させるか。その答えの一つが、ラレーのフレームにはあるように思います。
MTBのレジェンドが作る至高のロードフレーム Ritchey
マウンテンバイクの世界を創り上げた「レジェンド」の一人、トム・リッチー。彼が自らの名を冠して立ち上げたブランドがRitchey(リッチー)です。彼の作るフレームは、ただ軽いとか、ただ硬いとか、そういう単純な言葉では表せません。何千、何万という時間をサドルの上で過ごしてきた彼だからこそ分かる「自転車の気持ちよさ」が、フレームの隅々にまで宿っている。そんな感じです。
注目の軽量モデルをスペック比較
それでは、先ほどの基準(Cross-Check:約3.2kg)と比較しながら、具体的なプロダクトを見ていきましょう。
Panasonicを代表するプロダクト「FRCC24 / ORCC24」
パナソニックの公式サイトによると、TANGEプレステージを使用した軽量モデルでフレームの参考重量が1,790g〜と公表されています。KAISEIの特注パイプを使うこのモデルも、それに準ずる軽さを実現していると考えていいでしょう。オーダーメイドなのでサイズや仕様によって変動しますが、軽量クロモリフレームの代表格です。
RALEIGHを代表するプロダクト「CRR Carlton-R」
レイノルズの最高級ステンレスチューブ「931」を採用したフレームは、単体重量で約1.8kg台という驚異的な軽さを誇ります。基準となるCross-Checkのフレームと比較すると、その差は歴然ですね。
Ritcheyを代表するプロダクト「Road Logic」
独自のトリプルバテッドチューブを採用したフレームが約1,750g、付属のカーボンフォークが約350gと、合わせて約2.1kg(2,100g)という驚異的な軽さを実現。クロモリロードの定番でありながら、その軽さは一級品です。
重量差が一目瞭然!比較表
| ブランド | モデル | フレームセット参考重量 | 基準との重量差 |
| SURLY | Cross-Check | 約 3,200g | 基準 |
| Panasonic | FRCC24 / ORCC24 | 約 2,350g | – 約 850g |
| RALEIGH | CRR Carlton-R | 約 2,200g* | – 約 1,000g |
| Ritchey | Road Logic | 約 2,100g | – 約 1,100g |
※RALEIGHはフレーム単体重量からの推定値
まとめ
さて、今回は「軽さ」をテーマに現代のクロモリロードフレームを見てきましたが、いかがでしたでしょうか。
クロモリフレームにおける「軽さ」は、単なる数値上のスペックではありません。それは、ビルダーやブランドが、どういう走りを実現したいかという「哲学」の表れなんだと僕は思います。
SURLYのように、タフさや汎用性を重視して敢えて重量を厭わないフレームもあれば、今回紹介したフレームのように、伝統的な素材の可能性を信じ、最新の技術や知見を注ぎ込んで「軽さ」と「走り」を追求するフレームもある。どちらが優れているという話ではなく、どちらが自分の乗り方やスタイルに合っているか、ということです。
軽いフレームは確かに魅力的ですが、それがあなたの自転車ライフを最高にしてくれる唯一の解とは限りません。この記事が、あなたのクロモリフレーム選びの何か少しでも参考になれば嬉しいです。
皆さんが気になっている軽量クロモリフレームがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね!
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!