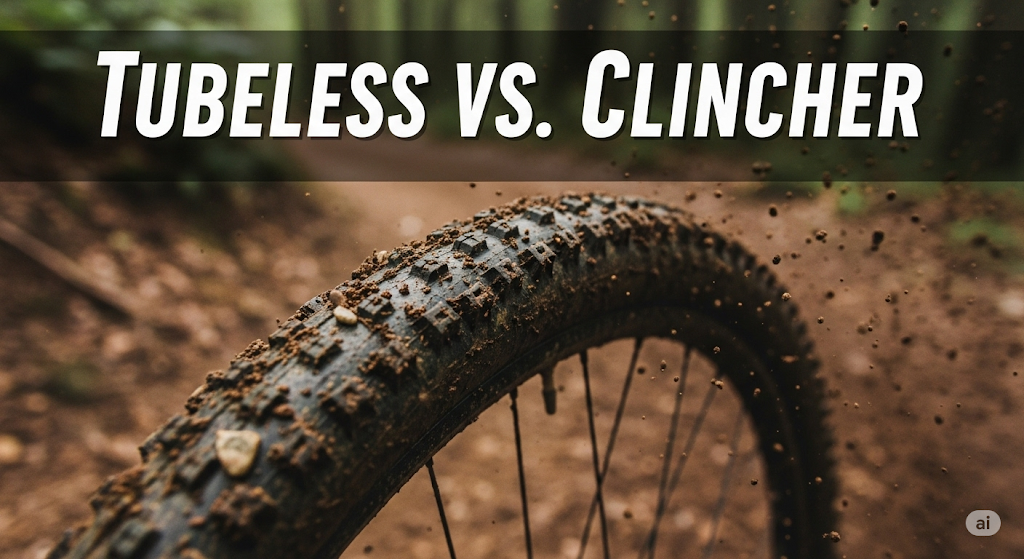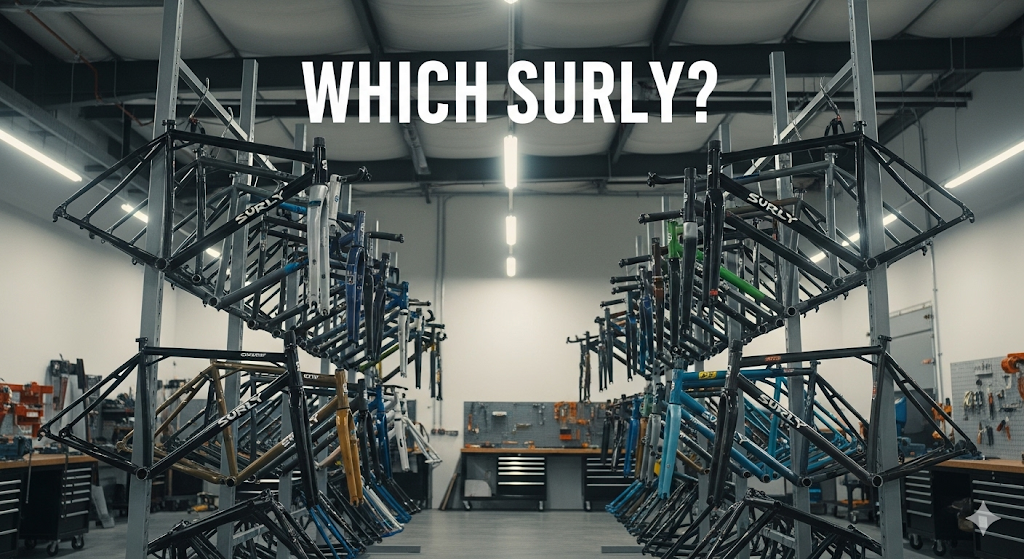錆だらけのマディフォックス、復活への道。オールドMTBレストアの沼へようこそ

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕の自転車ライフに新たな仲間が加わった話、そして、その仲間がもたらしてくれた「沼」への入り口についてのお話をしたいと思います。
ひょんなことから1995年製のARAYA Muddy Fox、モデル名も「SPICE StreetPerformer」という、なんとも時代を感じさせる一台を手に入れる機会がありました。
しかも、紫から青へと移り変わるフェードカラーが、もう本当に「ゲキシブ」なんです。オールドMTBと呼ばれる、80年代〜90年代のクロモリフレームのMTB。この時代のMTBが持つ独特の雰囲気、細身のクロモリフレームの美しさに、僕は以前からずっと心を惹かれていました。
しかし、この美しいフェードカラーのフレームとは裏腹に、僕の元にやってきたマディフォックスは、一見すると「満身創痍」という言葉がぴったりの状態。長年、雨風にさらされていたのでしょうか。フレーム以外のパーツは、チェーンも、ギアも、ボルト一本に至るまで、見事にもれなく錆びついていました。
でも、驚いたことに、あれだけ錆びているのにパーツの固着は一切ないんです。クランクもヘッドパーツもスムーズに回り、フレームの内部を覗いても、中は驚くほどきれいな状態でした。おそらく、屋根のある屋外ガレージのような場所で、長年眠っていたのかもしれませんね。だからこそ、表面的な錆はひどいけれど、自転車の心臓部はしっかりと生きている。
この事実に気づいた時、僕の心は決まりました。「これは、面白いことになりそうだ」と。
そう、僕はこのマディフォックスを、自分の手で復活させることに決めたんです。これは、単なる修理じゃない。一台の自転車と向き合い、その歴史に触れ、新たな命を吹き込む「レストア」という名の冒険の始まりです。
今回の記事では、このレストアプロジェクトの序章として、なぜ僕がオールドMTBに惹かれるのか、そしてこの錆だらけのマディフォックスをどんな一台に仕上げていきたいか、その妄想と計画についてお伝えしたいと思います。
なぜ今、オールドMTBなのか?ブームの背景と僕なりの考察
ここ数年、僕のような自転車好きの間で、静かに、しかし確実に「オールドMTB」のムーブメントが広がっているのを感じます。
最新のカーボンフレームや電動コンポーネントを搭載した高性能なMTBとは対極にある、クロモリフレームの古いMTB。なぜ今、これほどまでに注目を集めているのでしょうか。
僕なりに考えてみると、いくつかの理由が思い浮かびます。
一つは、「スタイルの多様性」。当時のMTBは、今の洗練されたMTBとは違い、どこか武骨で、デザインにも自由な遊び心がありました。そのフレームをベースに、現代のパーツを組み合わせて、街乗り用のクールなコミューターにしたり、荷物を積んで旅に出るバイクパッキング仕様にしたりと、オーナーの個性を反映した自由なカスタムができる。この懐の深さが、多くの人を惹きつけているんだと思います。
そしてもう一つは、「モノとしての魅力」。大量生産、大量消費が当たり前になった現代において、一本一本丁寧に作られたクロモリフレームの自転車が持つ、普遍的な美しさや、長く使える堅牢さが見直されているのではないでしょうか。デザイナーという仕事柄、僕は製品の背景にあるストーリーや哲学に強く惹かれます。オールドMTBには、まさにそうした「物語」が詰まっているんです。
このブームは、単なる懐古趣味ではなく、現代の価値観に対する一つのカウンターカルチャーのような側面も持っているのかもしれません。
レストアの醍醐味。それは「対話」と「創造」のプロセス
ここからが、僕がこのレストアという行為にどうしようもなく惹かれる理由です。それは単なる作業ではなく、一台の自転車の「過去」を読み解き、その「未来」を自分の手でデザインしていく、最高にクリエイティブな時間だからです。
「対話」とは、モノの来歴を読み解く面白さ

まずは分解作業。レンチを手に、一つ一つのボルトを慎重に緩めていきます。手に伝わる感触、工具の音、染み付いたオイルの匂い。五感のすべてを使いながら、この自転車が過ごしてきた時間を想像するのは、まるで探偵のような面白さがあります。
すり減ったペダルの踏面からは、前のオーナーがどんなシューズで、どんな風にペダルを漕いでいたのかが垣間見える。フレームに残された小さな傷は、どこかで一度、派手に転んだ記憶かもしれない。これらの痕跡は、まさにこの自転車が生きてきた証。ただの中古品ではなく、一つの物語を持った存在として、急に愛おしく見えてくるんです。
そして、分解したパーツを磨き上げる工程。これがまた、強烈な達成感を味わえる瞬間です。真っ黒な油汚れに覆われたディレイラーから、丹念に汚れを落としていくと、くすんでいた金属が輝きを取り戻し、隠れていたメーカーのロゴが誇らしげに現れる。錆びたネジの頭を磨き上げ、本来の銀色が見えた時の喜び。
これは、ただ綺麗にするだけじゃない。そのモノが作られた当時に持っていたはずの機能美や、作り手のこだわりを、自分の手で「再発見」していく作業なんです。この感動が、レストアの大きな原動力になっています。
「創造」とは、未来の姿をデザインする興奮

やて全てのパーツが外され、紫と青の美しいフレームだけが残ります。
僕にとってこの瞬間は、クライアントから依頼を受け、新しいデザインを前にした時の感覚によく似ています。ここにあるのは、確かな品質と歴史を持った最高の「素材」。この素材をどう活かし、どんな新しい価値を与えるか。デザイナーとしての腕の見せ所です。
どんな一台に仕上げるか。ここからは、無限の選択肢と向き合う、楽しくも悩ましい時間です。
例えばハンドル一つ選ぶにしても、単に形だけで選ぶのではありません。BMX風のハイライズなバーを選べば、街中を軽快に遊びまわる「やんちゃな相棒」になるだろう。大きく手前に湾曲したクランカーバーなら、休日の午後をゆったりと流す「穏やかなパートナー」になるかもしれない。
ブレーキは?タイヤの太さは?サドルの色は?一つ一つのパーツ選びが、完成する自転車の「キャラクター」を決定していく。機能性、デザイン性、そしてコスト。様々な要素を天秤にかけながら、頭の中にある漠然としたイメージを、具体的なパーツの組み合わせへと落とし込んでいく。このプロセスは、まさにデザインそのものであり、僕が最も興奮する時間です。
こうして過去を読み解き、未来をデザインする。この両方を自分の手で体験できるからこそ、完成した自転車は世界に一台だけの、特別な「自分の作品」になるのだと思います。
無限の可能性!どんなビルドにするか、妄想が止まらない

まだバラしてもいないうちから、どんな自転車に仕上げようかと妄想は膨らむばかりです。今のところ、僕の中にはいくつかの候補があります。
最近はAIがイメージも作ってくれるので、こうやって出来上がりのイメージを各パーツごとに決めていって見ることも出来るんだから楽しいものです。
候補1:オリジナル尊重レストア
まずは、マディフォックスが発売された当時の姿をできるだけ忠実に再現するビルド。オリジナルのパーツを探し出し、当時の雰囲気をそのままに蘇らせる。これはこれで、非常に魅力的です。自転車の歴史に対するリスペクトが詰まった一台になるでしょう。
でも、これには大きなハードルが。元のサスペンションフォークが完全に死んでいるのです。
MANITOU ANSWERのコピーモデルでしょうか、もともとTANGEのサスペンションフォークが完全に下付きしていて、純正の修理パーツももう出てるはずもなく。これは大きな障害になりそうです。
候補2:現代パーツで快適に!「レストモッド」スタイル
フレームの持つクラシックな雰囲気は活かしつつ、ブレーキやドライブトレインといったコンポーネントは現代の高性能なパーツに交換する「レストモッド」というスタイル。見た目はクラシック、でも走りは快適。普段の街乗りから週末のサイクリングまで、気兼ねなく使える相棒になってくれそうです。
候補3:カゴとラックで実用的に「コミュータースタイル」
前後にキャリアやバスケットを取り付けて、日々の買い出しや通勤を快適にするコミューター(街乗り)仕様。少しアップライトなハンドルバーに交換して、ゆったりとしたポジションで大阪の街を流す。そんな姿を想像するだけで、楽しくなってきます。
候補4:旅に出たくなる「バイクパッキングスタイル」
フレームバッグやサドルバッグを取り付け、どこへでも冒険に出かけられるバイクパッキング仕様。太めのブロックタイヤを履かせて、舗装路だけでなく、ちょっとしたダートも走れるようにする。このマディフォックスで、まだ見ぬ景色を探しに行く旅もいいですね。
候補5:BMXみたいに遊びたい「ストリートスタイル」
思い切って変速機を取っ払い、シングルスピード化。ハンドルをBMXのようなハイライズなものに交換して、街中の段差やスロープで遊びたくなるような一台に。MTBの持つタフさとBMXの軽快さを両立させた、まさに「Street Performer」の名にふさわしいスタイルかもしれません。
候補6:原点回帰の「クランカースタイル」
MTBのルーツである「クランカー」の雰囲気を再現するビルド。ビーチクルーザーに使われるような、大きく手前に引いたハンドルバーを取り付け、シンプルで武骨なスタイルに仕上げる。最新のトレンドとは真逆を行く、究極に力の抜けたカッコよさ。これもまた、たまらなく魅力的です。
日本のMTB黎明期を支えたARAYA(アラヤ)とMuddy Fox(マディフォックス)
ここで、僕が手に入れた「ARAYA Muddy Fox」について少し触れておきたいと思います。
ARAYA(新家工業)は、1903年に創業した日本の老舗自転車部品メーカーです。特に自転車のリム(車輪の輪の部分)のメーカーとして世界的に有名で、その品質の高さは多くのサイクリストから信頼されています。
そんなARAYAが、日本でマウンテンバイクという文化が黎明期にあった1982年に発売したのが、日本初の本格的MTB「マディフォックス」でした。当時、アメリカ西海岸で生まれたばかりのMTBという新しい自転車を、日本のフィールドに合わせて開発し、国内に広めた立役者の一つと言えるでしょう。
僕が手に入れた95年製の「SPICE StreetPerformer」は、まさにそんな時代の空気感をまとった一台。マウンテンバイクが多様化し、ストリートへと繰り出すスタイルも生まれた、そんな過渡期のモデルかもしれません。そのフレームには日本の自転車史の一部が宿っている。そう思うと、このレストアプロジェクトが、さらに意義深いものに感じられてきます。
仲間たちを探して。マディフォックスと同時代の国産名車たち
僕のマディフォックスのように、80年代後半から90年代にかけては、日本の自転車メーカーがこぞって個性的なMTBを世に送り出した、まさに黄金時代でした。もし皆さんがオールドMTBの世界に足を踏み入れるなら、こんな「仲間たち」の存在も知っておくと、より一層楽しめるはずです。
MIYATA Ridge-Runner(ミヤタ リッジランナー)
マディフォックスの最大のライバルと言えば、やはりミヤタのリッジランナーを置いて他にはないでしょう。早くから自社で高品質なクロモリパイプを製造していたミヤタならではの、しなやかで力強い乗り味は多くのファンを魅了しました。特に、フレームのラグ溶接の美しさは特筆もので、工芸品のようなオーラを放っています。
Panasonic Mountain Cat(パナソニック マウンテンキャット)
ナショナルブランド時代から続く自転車作りのノウハウと、パナソニックの持つ最新技術を融合させて生まれたのがマウンテンキャットです。特徴的なのは、他のメーカーに先駆けてアルミフレームやカーボンフレームのモデルを積極的に投入していたこと。当時のカタログを眺めているだけでも、その先進性にワクワクさせられます。クロモリモデルももちろん名作揃いです。
Bridgestone Wild West(ブリヂストン ワイルドウエスト)
日本の自転車業界の巨人、ブリヂストンが展開していたのがワイルドウエストシリーズです。トップモデルには、アメリカの伝説的ビルダー、リッチー・カニンガムが設計に関わったモデルも存在するなど、その本気度が伺えます。豊富なラインナップと、ブリヂストンらしい真面目で堅実な作りが魅力の一台です。
これらの自転車は、どれも日本のモノづくりの情熱が詰まった名車ばかり。中古市場やガレージの奥で、再び光が当たるのを待っているかもしれません。
まとめ:錆の向こう側に見える、新たな自転車との出会い
というわけで、今回は僕の新たなプロジェクト「マディフォックス レストア計画」の始まりについてお話ししました。大人になってから26インチの自転車は初めて触るので、組みだす前からどんな乗り感だろう、と本当にワクワクしています。
目の前にあるのは、表面は錆だらけでも、心臓部はしっかりと生きている一台の古い自転車。僕にはこれが宝の山に見えています。これから、この鉄の塊がどんな風に姿を変えていくのか。そして、完成した暁には、どんな素晴らしい走りを見せてくれるのか。想像するだけで、胸が高鳴ります。
このブログでは、今後のレストアの進捗状況も、成功も失敗も含めて、赤裸々にレポートしていきたいと思っています。僕のマディフォックスが最終的にどんな姿に生まれ変わるのか、皆さんもぜひ楽しみにしていてくださいね。途中経過や完成の暁には、このブログはもちろん、SNSでもお知らせするつもりです!
皆さんのガレージや家の隅にも、もしかしたらそんな「お宝」が眠っているかもしれませんよ。
この記事を読んで、オールドMTBのレストアについて思ったこと、あるいは「自分もこんなレストアをしたことがある!」といった経験談などがあれば、ぜひ下のコメント欄で教えてください。皆さんの声が、僕の励みになります。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!