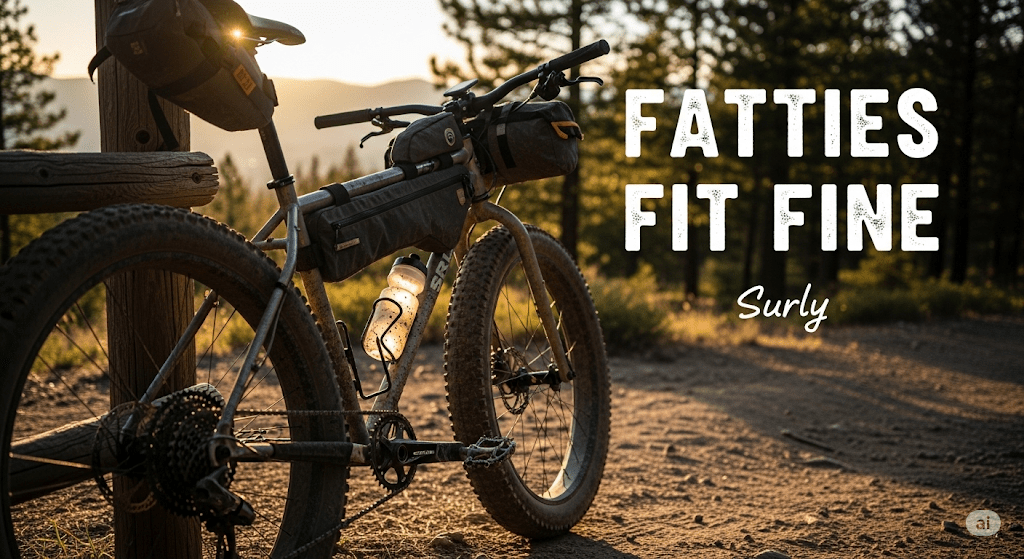MIYATA(ミヤタ)の自転車は日本の誇り。130年以上の歴史と哲学を紐解く。

こんにちは、ヒロヤスです。大阪の街を今日も自転車で駆け抜けているアラフォー、デザイナーの僕です。
僕のブログをいつも読んでくださっている皆さん、本当にありがとうございます。さて、今回は、僕たちが愛してやまない日本の自転車ブランドの中でも、特に長い歴史と、確固たる哲学を持つ「MIYATA(ミヤタ)」について、その魅力を深く掘り下げてお伝えしたいと思います。
MIYATAと聞くと、どんなイメージが浮かびますか? E-BIKEに強い、あるいはクラシカルな自転車を作っている、など様々な印象があるかもしれません。しかし、その根底には、130年以上にもわたって受け継ぎてきた、日本のモノづくりへの情熱と誇りが脈々と流れています。今回は、その歴史の深淵から、現代に生きるクロモリフレームの魅力まで、じっくりと紐解いていきましょう。
MIYATAの原点:鉄砲鍛冶から自転車製造への道
MIYATAの歴史は、なんと1881年(明治14年)、東京の地で始まります。
創業者の宮田栄助氏は、もともと鉄砲を製造する「宮田製銃所」を営む腕利きの職人でした。転機が訪れたのは1889年。一人の外国人が持ち込んだ、当時最先端だった「安全型自転車」の修理を依頼されたことが、MIYATAと自転車の出会いでした。鉄パイプを加工する銃づくりの技術が、自転車フレームの製造に応用できることを見抜いた栄助氏は、自転車の将来性に着目し、その製造を決意します。
そして1890年(明治23年)、ついに日本で初めてとなる安全型自転車の製造を開始。これが、日本の自転車産業の幕開けとも言える、MIYTAブランドの誕生の瞬間でした。鉄砲鍛冶として培った精密な金属加工技術が、MIYATAの自転車づくりの礎となったのです。
東京で産声を上げたMIYATAは、現在、神奈川県足柄上郡に本社を構え、日本の自転車文化を支え続けています。
日本の自転車史そのもの。MIYATAが刻んだ栄光
MIYATAの歩みは、まさに日本の自転車の歴史そのものです。
国産初の自転車を製造して以降も、その技術力で業界をリードし続けます。特に有名なのが、フレームパイプの接合に電気溶接を用いる「フラッシュ・バット製法」を実用化したこと。これにより、高品質なフレームの大量生産を可能にし、日本のトップメーカーへと駆け上がりました。
その名は国内に留まらず、世界にも轟きます。1970年代後半からは本格的にスポーツバイクの輸出を開始。ヨーロッパの強豪プロチームにフレームを供給し、なんと1981年には、日本製フレームとして初めてツール・ド・フランスで区間優勝を果たすという快挙を成し遂げました。
この快挙を支えたのが、MIYATAが独自に開発した「SSTB(スパイラル・スプライン・トリプル・バテッド)」チューブです。クロモリチューブの内側に螺旋状の補強リブを入れることで、軽量でありながら高い剛性を実現するという画期的な技術でした。このSSTBチューブは、今もなおMIYATAのクロモリフレームの魂として受け継がれています。
MIYATAを代表する現行クロモリプロダクト
まずは、現在も僕たちが手にすることができる、MIYATAの伝統を受け継ぐクロモリバイクたちをご紹介します。
The Miyata FRAME SET(ザ・ミヤタ フレームセット)
ツール・ド・フランスを制した伝説のフレームのDNAを受け継ぐ、ブランドの象徴とも言える一本。独自のSSTBチューブを採用し、高剛性としなやかさを絶妙なバランスで両立させています。熟練の職人による丁寧なメッキ処理と塗装の仕上げは、まさに工芸品の域。
このフレームは、自分の理想の一台をじっくりと組み上げたいサイクリストに最適です。クラシカルなパーツで組んで往年のロードレーサースタイルを再現するもよし、最新のコンポーネントでネオクラシックな一台に仕上げるもよし。乗り手の個性を最大限に引き出してくれる、懐の深いフレームです。
ITAL SPORT(イタルスポーツ)
SSTBクロモリチューブとカーボンフォークを組み合わせた、現代的なロードバイクです。クロモリならではの振動吸収性の高さと、カーボンフォークによるシャープなハンドリングが融合。路面からの細かな振動をいなしつつ、軽快な走りを楽しめます。
週末のロングライドから、ちょっとしたサイクリングまで、幅広い用途に対応できるのが魅力。細身のホリゾンタルフレームは、街乗りでも美しく映えます。初めてのクロモリロードバイクとしても、非常におすすめしやすいモデルです。
FREEDOM+(フリーダムプラス)
自転車旅のために生まれた、クロモリフレームのグラベルロード。太めのタイヤを装着できるクリアランス、キャリアを装着するためのダボ穴など、バイクパッキングやツーリングに必要な機能が満載です。
舗装路の軽快さはもちろん、未舗装の林道にも臆することなく分け入っていける走破性がこのバイクの真骨頂。日々の通勤から、荷物を満載してまだ見ぬ景色を探しに行く週末の冒険まで、あなたの「自由」な旅の最高の相棒となってくれるはずです。
時代を彩ったMIYATAの伝説的な名車たち
次に、今は生産されていなくとも、多くのサイクリストの記憶に残り、MIYATAの歴史を語る上で欠かせない伝説のモデルたちを見ていきましょう。
Le Mans(ル・マン)
1970年代から80年代にかけて、日本のサイクリング文化を牽引したツーリングバイク(ランドナー)の名車です。当時、多くの若者がこの「ル・マン」にサイドバッグを取り付け、日本中を旅しました。美しく設計されたラグ付きのクロモリフレーム、泥除けやダイナモライトを備えた姿は、まさに旅自転車の王道。この一台に憧れ、自転車旅の魅力に目覚めた方も少なくないはずです。
Ridge Runner(リッジランナー)
日本のマウンテンバイクの歴史を切り拓いた、伝説的なモデルです。1980年代初頭、まだ日本にマウンテンバイクという概念すらなかった時代に、MIYATAはいち早くその可能性に着目し、このモデルを世に送り出しました。SSTBチューブを採用した頑丈かつ軽量なクロモリフレームは、当時の他のどんな自転車とも一線を画すものでした。
当時人気を二分したARAYAの「マディフォックス」やPanasonicの「マウンテンキャット」といったライバル社のモデルよりも、やや高価格帯の高級機として位置づけられていたことも、MIYATAの技術力への自信の表れと言えるでしょう。 山道を駆け下るという新しい自転車の楽しみ方を、日本のサイクリストに教えてくれたのが、このリッジランナーだったのです。
まとめ:MIYATAが僕たちに教えてくれること
今回は、日本の誇る自転車ブランド、MIYATAの歴史と哲学、そして現代に生きるクロモリバイクについてお伝えしました。
「The Miyata」や「ITAL SPORT」のような現行モデルには、ツール・ド・フランスを制した栄光の技術が今も息づいています。一方で、「ル・マン」や「リッジランナー」といった過去の名車たちは、日本のツーリングやMTBといった自転車文化そのものを創り上げてきました。
鉄砲鍛冶から始まったMIYATAの歴史は、常に時代の最先端を走り、日本のモノづくりの質の高さを世界に証明してきた歴史です。その伝統におごることなく、誠実に自転車と向き合い続ける姿勢。それこそが、MIYATAが130年以上もの長きにわたって愛され続ける理由なのだと、僕は思います。
一本の自転車に込められた物語を知ることで、僕たちの自転車ライフはさらに豊かなものになります。MIYATAの自転車に乗るということは、日本の自転車の歴史そのものを体感することなのかもしれませんね。
この記事を読んで、MIYATAの自転車に興味を持っていただけたら嬉しいです。皆さんの好きなMIYATAのモデルや、思い出などがあれば、ぜひコメントで教えてください。
それでは、また次の記事で会いましょう!ヒロヤスでした!